平成30年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題8解説
問1 文化化
主に幼少期に周囲の人々やメディアなどから当該文化の習慣や常識、ルール、価値観、考え方を教わり身につけていくことを文化化と呼びます。
選択肢4の記述がそれです!
答えは4。
問2 カルチャー・ショック
カルチャーショックは異文化に触れたときに生じる心理的・身体的ストレス反応のことです。生活習慣が違ったり、言語そのものが違ったり、考え方が違ったり、食べ物が違ったりといろんな原因で生じます。旅行とか短期のものだとあまり生じないですが、長期的に異文化に滞在する人はカルチャーショックを経験します。

選択肢1
ハネムーン期の記述です。ハネムーン期は見るもの全部が新鮮で楽しさが前面に現れる期間です。短期旅行ではこのハネムーン期しか経験しないので滞在中はずっと楽しい状態が続きますが、長期滞在だと最初のハネムーン期を超えるとカルチャーショック期を迎えるとされています。
選択肢2
カルチャーショックは精神的なものだけでなく、身体的症状として現れることもあります。それこそ食欲低下、疲労、頭痛、睡眠不足など… これが答え。
選択肢3
自国でも文化や習慣、価値観が異なれば経験することもあります。例えば進学、就職して故郷から離れたりすると、友達がいなかったり、言葉が違ったり、それまでの友達がいなかったりと環境の変化が生じます。それによってカルチャーショックが起こることがあります。
選択肢4
カルチャーショックは瞬間的なものではなく、持続的なものです。長い間カルチャーショックにさらされ、それを徐々に乗り越えていくと適応の段階を迎えます。
したがって答えは2です。
問3 Wカーブ
Uカーブに帰国後の適応過程を加えたものをWカーブ仮説と言います。

簡単に説明しますと、Wカーブ仮説では異文化に行ったあとにカルチャーショック期を迎え、それがだんだん適応してきた段階で帰国し、帰国後にまたリエントリーショックという一種のショックを経験したのち、また再適応すると考えます。
選択肢1
正しいです。Wカーブは異文化適応過程と帰国後の自文化適応過程を表した曲線です。そしてカルチャーショックとリエントリーショック、どちらがひどいかは人によります。リエントリー・ショックがひどい場合もあります。よほど滞在国の文化に馴染んでしまった場合は自国の文化によりショックを受けてしまうかもしれません。
選択肢2
Wカーブは不適応状態を示したものではなく、適応の段階を示したものです。Wカーブ曲線では異文化になじめないまま帰国した人の適応過程を表したものではなく、異文化になじめた人が帰国した場合の過程を示すものです。この選択肢は間違い。
選択肢3
Wカーブは周囲との接触の度合いを示したものじゃないです。この選択肢は間違い。
選択肢4
Wカーブは異文化から帰国した後の適応段階を示すのではなく、異文化への移動後と帰国した後の適応の段階を示したものです。
したがって答えは1です。
問4 文化変容(acculturation)
問題文を見ると「文化変容」と「ベリー」というキーワードがあります。ここから思い出したいのは文化変容ストラテジー。ベリーは①自分のアイデンティティを維持するかしないか、②滞在国の人と関係をどれだけ持つかどうかの2つの態度によってその人を取り巻く環境を説明しています。

選択肢1
「自文化に閉じこもっている状態」で文化だということが分かります。異文化を取り入れようとすると自分の中の習慣とか価値観、行動芳樹などが変化しますが、自文化に閉じこもると異文化のあれこれをシャットダウンして自分の中に取り込もうとしなくなるので「変化が最も小さく」なります。これが答え。
選択肢2
これは同化です。自文化を喪失して異文化に馴染んでいるので、異文化の習慣、価値観、行動様式などをどんどん自分の中に取り入れていくことができます。文化的・心理的に受容が最も大きいとはこういうことです。
選択肢3
周辺化。自文化を喪失して、異文化にも馴染めていない状態です。
選択肢4
これは統合です。自文化も異文化も両立できている、一番理想的な状態です。
したがって答えは1。
問5 ソーシャルサポート
社会的関係の中でやりとりされる学習者への支援のことをソーシャルサポートと言います。
選択肢1
正しいです。必要なものを提供できたら、それは一番いいサポートになります。
選択肢2
正しいです。相当ストレスが強くてサポートもくそもない状態になることも考えられますね…
選択肢3
正しいです。相手の問題をしっかり見極めたサポートをすべき。
選択肢4
同じような困難を抱えた者からのサポートによって「同じような人がいるんだ!」と安堵できたり、お互い話し合って自分の状況を客観的に見れるようになったりして問題解決できる可能性が高まります。
答えは4です。



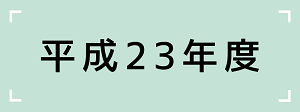
コメント
コメント一覧 (2件)
毎日見させていただいています。
この解説サイトのお陰で、勉強が進められています。
全くの未経験、かつ、周りにこの試験のことを知っている人もいないし、一緒に受ける人もいません。
なぜこの試験を受けることになったのかというと、
会社で留学生を受け入れており、
日本語学校だけでなく、会社でも補講的な形で教えようとなったことから、私が受けることになりました。
420時間の講習を受けるには隣県まで行かないと受けられませんので、検定試験を受けるということになりました。
テキストを読んでも呪文を読んでいるようでさっぱりわからず眠くなる日々から、なんとかやってきましたが、このサイトのおかげで勉強を続けられています。感謝の気持ちを伝えたくてコメントをさせていただきました。
渡辺と申します。
場面シラバスと、概念・機能シラバスは内容的に同じもののようにおもいますが、
具体的な違いはどこにあるのでしょうか?