令和3年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題14解説
問1 フェイス
まずポライトネス理論から説明します。
ポライトネス理論とは、人はお互いのフェイスを傷つけないように配慮を行いながらコミュニケーションを行っているとする理論のことです。この理論ではフェイスとポライトネス・ストラテジーが重要な概念となっています。
| フェイス | 人と人の関わり合いに関する欲求のこと。このうち共感・理解・好かれたいことを望む欲求をポジティブ・フェイスといい、邪魔されたくない、干渉されたくないという自由を望む欲求をネガティブ・フェイスといいます。 |
|---|---|
| ポライトネス・ストラテジー | 会話において両者が心地よくなるよう、あるいは不要な緊張感がないように配慮するなど、人間関係を円滑にしていくための言語行動のこと。そのうち、相手のポジティブ・フェイスを確保しようとする言語行動をポジティブ・ポライトネス、相手のネガティブ・フェイスを侵害しないようにする言語行動をネガティブ・ポライトネスと呼びます。 |
とりあえずこれは基本情報。
選択肢1
ポジティブ・フェイスは相手に近づきたいという欲求なので、「立場をわきまえて行動したい」という欲求とは逆に見えます。これはどちらかというとネガティブ・フェイスの記述。この選択肢は間違いです。
選択肢2
その言語行動が相手のフェイスを侵害するリスクが低い場合、その言語行動は遂行されやすいです。例えば「これ手伝って」と言って相手が嫌がる(ネガティブ・フェイスを脅かす)可能性が高いと判断すれば、その言語行動は回避されます。
行為回避が行われるのは相手のフェイスを侵害するリスクが高い場合です。この選択肢は間違い。
選択肢3
ここでいう「フェイスに配慮する」とは、「聞き手のポジティブ・フェイスに配慮する」もしくは「聞き手のネガティブ・フェイスに配慮する」の2択です。どちらにしても相手に配慮するわけなので、その配慮が必要かどうかは文化によって異なるのではなく、相手によって異なります。この選択肢は間違い。
選択肢4
フェイスを侵害する度合い(FTA)は次のような公式で表されます。
Wx=D(S,H)+P(S,H)+Rx
Wxはある行為が相手のフェイスを脅かす度合い、D(S,H)は話し手と聞き手の社会的距離、P(S,H)は話し手と聞き手の相対的権力、Rxはある行為の特定文化における押しつけがましさの程度を表します。
この選択肢にある「文化」はRxのことであり、RxはWxを決定する変数の一つ、すなわち文化が異なればフェイスを侵害する度合いは異なります。これが答え。
答えは4です。
問2 FTA
問1の選択肢4ででてきたフェイスを侵害する度合い(FTA)を表す公式を使います。
Wx=D(S,H)+P(S,H)+Rx
フェイスを侵害する度合い(Wx)は、話し手と聞き手の社会的距離(D(S,H))、話し手と聞き手の相対的権力(P(S,H))、ある行為の特定文化における押しつけがましさ(Rx)によって決まります。この3要素と比較して選択肢を見てみます。
1 こんなものはない
2 ある行為の特定文化における押しつけがましさ
3 話し手の聞き手の相対的権力
4 話し手と聞き手の社会的距離
選択肢1はWxを決める変数に含まれてません。
答えは1です。
問3 敬語
1 「伺う」は謙譲語Ⅰ
2 「参る」は謙譲語Ⅱ
3 「いたす」は謙譲語Ⅱ
4 「申す」は謙譲語Ⅱ
謙譲語Ⅰと謙譲語Ⅱはどちらも自分の行為に使うタイプの敬語ですが、謙譲語Ⅰは相手に向かう自分の行為に対して使い、謙譲語Ⅱは向かう相手がいない自分の行為に使います。この説明は本当に簡易的なんで… もし気になる方は「謙譲語Ⅰと謙譲語Ⅱの違い」をご覧ください。
それを知らなくても暗記だけで解くこともできます。
謙譲語Ⅱはもう数えるほどしかありません。動詞だったら「参る、申す、いたす、おる、存じる」です。この5つをそのまま覚えておけば、選択肢1「伺う」は謙譲語Ⅰ、それ以外はⅡだと分かります。
よって答えは1です。
参考:敬語の指針 – 文化庁
問4 二重敬語
一つの語に対して同じ種類の敬語を二重に使ったものを二重敬語と言います。
選択肢1
「案内(する)」に謙譲語Ⅰ「お/ご~申し上げる/申し上げます」をつけて「ご案内申し上げる」としているだけ。これは一重敬語。
選択肢2
「聞いてもらう」の「聞く」を謙譲語Ⅰ「伺う」にして、「もらう」を謙譲語Ⅰ「いただく」にしています。一つの語「聞く」と「もらう」に一つずつ敬語を使っているだけなので二重表現ではありません。
このように二つ(以上)の語をそれぞれ敬語にして接続助詞「て」でつなげたものを敬語連結と言います。
選択肢3
「言う」の尊敬語は「おっしゃる」で、これにさらに尊敬表現「~られる」をつけています。
一つの語「言う」に2つの尊敬表現がついています。これが二重敬語。
選択肢4
元々の言い方は「話していました」です。
まず「話す」に尊敬表現「お~になる」をつけて、「お話になる」とします。
次に「いる」を尊敬語にして「いらっしゃる」としています。
2つの語をそれぞれ尊敬表現にしているだけで選択肢2と同じ敬語連結。二重敬語ではありません。
したがって答えは3です。
問5 語用論的指導
極端な例だけど… 友達と別れるときは「またね」って言いますが、店員さんはお客さんが退店するときに「またね」なんて言いません。どちらも”別れのとき”という共通点はあっても、その状況は全く違います。ことばはその状況に応じて使い分けられています。ここでいう状況は、語用論では「文脈(コンテクスト)」と呼ばれています。
この問題は敬語に関する問題なので、それでももう一例挙げます。
例えば上司に「やっと来られましたか」と言えても、友達には言えません。敬語は相手(文脈の一部)に応じて使い分けられます。
選択肢1
正しい記述です。上記の例だと、日本語母語話者はどんなときに「またね」を使い、どんなときに使わないのかを文脈との関係から考えさせるような指導は語用論的指導として有効です。
選択肢2
たしかに誤りの訂正を避けると自分は間違ってないと思うから発話意欲は向上します。
でもこの記述は語用論的指導と関係ないです。間違い。
選択肢3
相手が親しくない人だったら「窓を開けていただけますか?」などと敬語を使って配慮し、親しい人だったら「窓開けて」とか直接言ったり。聞き手という文脈によって表現を使い分けることを意識させるのは語用論的指導として有効です。
選択肢4
正しい記述です。ここでいう語用論的規範とは、「こういう場面ではこういう表現を使う」というルールのことで、これを明示的に教えるのは語用論的指導として有効です。例えば「友達と別れるときは『またね』というけど、先生やお客さんなどと別れるときは使わない」と規範を直接教えちゃうイメージです。
したがって答えは2です。
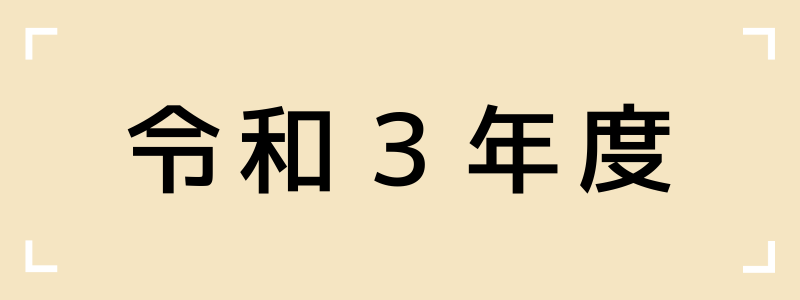


コメント