平成29年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題5解説
問1 使用語彙
1 基礎語彙の記述。日常生活でよく使う「寝る」「起きる」「食べる」「ご飯」とか。
2 理解語彙の記述。
3 使用語彙の記述。
4 基本語彙の記述。例えば日本語教育なら「一段動詞」「マス形」とかが基本語彙。
答えは3です。
問2 初級学習者にとって覚えやすい語の特徴
選択肢1
「屋」が共通しているので、そば屋、宿屋などと他にも応用しやすく覚えやすくなります。
選択肢2
中国語で電話をかけるは「打电话」、鍵をかけるは「锁门」です。日本語では同じ「かける」ですが、中国語では動詞が「打」と「锁」に分けられます。このようなケースは初級学習者にとって覚えにくいものとなります。日本語で同じく「かける」だからといって、外国語でも同じとは限らない。これが間違い。
選択肢3
「去年」や「来年」は日常生活で頻繁に使用する語ですので覚えやすいです。
選択肢4
例えば「承る」のようにモーラが多すぎると当然覚えにくくなります。
よって答えは2です。
問3 直示表現/ダイクシス
発話現場のコンテクストに依存して意味が決定する言語の性質をダイクシス(直示)といい、そのような表現をダイクシス表現(直示表現)と言います。例えば「これ食べてもいい?」という発話における「これ」が指すものは何かを理解するためには、その発話現場の状況を参照しなければなりません。具体的に言うと、その発話現場にいて「これ」が指しているものをその目で見なければ「これ」の意味が分からないということです。このとき「これ」は、その意味が発話現場の物理的なコンテクストに依存して意味が決まっていると言えます。「りんご」を指していれば「これ」の意味は「りんご」だし、「せんべい」を指していれば「これ」の意味は「せんべい」です。ダイクシス表現はその意味がコンテクストに依存しているので、コンテクスト次第で指し示す事物、意味が変わってきます。
このような直示性を持ったものを探してみましょう。
選択肢1
現場指示において「これ」「あれ」「それ」は全て発話現場にある事物を指し、コンテクストによって指し示す事物が変わるのでダイクシス表現です。また、指し示す事物の位置の違いもあります。例えば「これ」は、話し手と聞き手が位置的に対立している場所で会話しているとき、話し手の近くにあるものに対して「これ」と言いますが、Aさんが「これ」というとAさんの近くのものを指し、Bさんが「これ」というとBさんの近くのものを指します。「これ」が指す位置は話し手が誰かによっても変わります。
このような性質から、絵カードで「これ」「あれ」「それ」を導入する場合はむずい。単純に距離というと語弊があるけど、そういう人と人の距離感を絵カードに書かないと「これ」「それ」「あれ」の視覚的な導入ができないです。だからこの3つは気をつけないと。
選択肢2
「来る」と「行く」は今いる場所によって使い分けが生じる表現で直示的動詞ですが、「逃げる」は直示表現ではありません。
詳しくはこちら。
選択肢3
「あげる」「もらう」は物の与え手か受け手かによって使い分けが生じる表現で直示的動詞ですが、「捨てる」は直示表現ではありません。
選択肢4
「朝」「昼」「夕方」は直示表現ではありません。
したがって答えは1です。
問4 語の意味の指導
選択肢1
和語は漢語より易しいと断定しているのが気になります。少なくとも中華圏の学習者にとっては、漢語のほうが比較的簡単に習得できます。英語圏の学習者にとっては和語も漢語もほぼ同じ難易度じゃないかな? その人の母語によって変わるからこの選択肢は間違い。
選択肢2
例えば日本語の「読書」は文字通り本を読むという意味ですが、中国語の「读书」は「勉強をする」という意味を表します。また、中国語の「勉强」は「無理やり~する」という意味です。
このように、同じ単語でも意味が異なるケースがありますので注意が必要です。
選択肢3
英語が話せるからと言ってカタカナで書かれた外来語が分かるわけではありません。例えば、日本語の読み方で「アース」といっても、それが earth だと聞き取れるとは限らないし、「ガソリンスタンド」のような和製英語なんかもあるし。だから「外来語が易しい」というのは誤りです。
選択肢4
選択肢2で説明した通りです。同じ単語でも意味が違うものもありますので、指導する必要はあります。
答えは2です。
問5 スリーヒントゲームを行う意図
わりと面白そうなゲーム。
例では、「図書館」という語を「本がたくさんあります」「勉強ができます」「学生がたくさんいます」といった言い方をして説明し、聞いてる人に「図書館」と当ててもらっています。
選択肢1
上記の例だと、カードを見た学習者には習った語(既習語)「図書館」を見せています。この「図書館」を使って文を作らせるのは反則。いかに「図書館」という語を使わないで図書館を説明するかがこのゲームのおもしろいところ。この選択肢は間違いです。
選択肢2
これが答えです。ヒントを出す学習者には、「図書館」という習った語を別の語で説明する役割が課されます。その過程で「図書館」という単語を定着させることができそうです。これはカードを見た学習者に対する効果。
選択肢3
手順②はカードを見た学習者がすることなので、ヒントを与えられた学習者に対する効果を期待したものではありません。
選択肢4
手順②はカードを見た学習者がすることなので、ヒントを与えられた学習者に対する効果を期待したものではありません。
答えは2です。

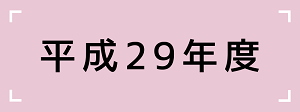


コメント
コメント一覧 (2件)
英語話者にとって外来語の取得は逆にとても難易度が高いと思います。カタコトの日本語を話すフランス人(日本在住の英語講師)の友人と、外来語取得の難しさを話すことがあります。カタカナが読める彼女がフラッシュカードに書かれていた「ローリングストーンズ」の意味を理解できませんでした。日本語のピッチアクセントに直されたストレスアクセントの外来語の取得は難しくと思います。
>井上さん
そうなんですね! 英語について詳しくないので想像で書いていました。
解説についてはコメントの内容を参考にし、修正いたします。
ありがとうございました!