平成29年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題3解説
問1 拘束形式
この問題はちょっと難しめです。
まず形態素は単独で語になれるかどうかで分類できます。
| 独立形態素自由形態素 | 単独で語になることができる形態素のこと。例えば、「雨風」は{ame}と{kaze}の2つの形態素からなる。そのいずれも「雨」と「風」というように単独で語になることができるため、「雨」も「風」も独立形態素。 |
|---|---|
| 拘束形態素束縛形態素 | 単独で語にならず、他の形態素とともに現れる形態素のこと。主に接頭辞や接尾辞など。例えば、「お電話」は{o}と{denwa}の2つの形態素からなる。{o}は接頭辞で単独で語となることができないため、拘束形態素に分類される。 |
それから、単独で用いることができるかどうかでも分類できます。
| 自由形式 | 単独で用いることができる形態素のこと。例えば、「あめ」は単独で「雨」や「飴」を表すことができるため自由形式。 |
|---|---|
| 拘束形式 | 単独で用いることができない形態素のことで、特定のより大きな形式の一部としてしか現れない形式を指す。例えば、「あめ」は単独で「雨」や「飴」を表すことができるため自由形式だが、「雨脚」の「雨」は「あま」と読み、「雨雲」「雨傘」「雨曇り」などの特定の語に付属して単独で意味機能を果たさない。 |
単独で語になれるかどうか、用いることができるかどうか。この2つは同じじゃないかって思うかもしれませんが違います。この辺りよく混同しますので注意してください。
選択肢1
{kin}は「金」にも「巾」にも「菌」にもなれますので、「金」は独立形態素です。
「金(きん)」はそのまま用いることができますので自由形式です。
{patu}は「髪」「発」などになれますので、「髪」は独立形態素です。
「髪(ぱつ)」は「銀」や「白」などの特定の語につかないと「ぱつ」と読みません。単独で用いることができず、その使用に制約があるので拘束形式です。
選択肢2
{saka}は「酒」「坂」「逆」などになれますので、「酒」は独立形態素です。
「酒(さか)」は「蔵」「場」などの特定の語につかないと「さか」と読みません。単独で用いることができず、その使用に制約があるので拘束形式です。
{gura}は「蔵」「倉」などになれますので、「蔵」は独立形態素です。
「蔵(ぐら)」は「酒」などの特定の語につかないと「ぐら」と読みません。単独で用いることができず、その使用に制約があるので拘束形式です。
選択肢3
{hina}は「雛」「比奈」などになれますので、「雛」は独立形態素です。
「雛(ひな)」は何かの語につかなくても「ひな」と読めます。それ単独で用いることができるので、自由形式です。
{maturi}は「祭り」「祀り」などになれますので、「祭り」は独立形態素です。
「祭り(まつり)」は何かの語につかなくても「まつり」と読めます。それ単独で用いることができるので、自由形式です。
選択肢4
{hana}は「花」「鼻」などになれますので、「鼻」は独立形態素です。
「鼻(はな)」は何かの語につかなくても「はな」と読めます。それ単独で用いることができるので、自由形式です。
ちなみに「団子鼻(だんごばな)」の「鼻(ばな)」だったら拘束形式です。
{gumori}は「曇り」になれますので「曇り」は独立形態素です。
「曇り(ぐもり)」は「花」などの特定の語につかないと「ぐもり」と読みません。単独で用いることができず、その使用に制約があるので拘束形式です。
したがって答えは2です。
問2 音韻的に異なる要素
1 [pi]と[bi]は異なる音韻
2 助詞「が」をつけてアクセントを見ると、「歯が」は高低、「葉が」は低高なので音韻的に異なる
3 [ha]と[wa]は異なる音韻
4 [o]と[o]は同じ音韻
したがって答えは4です。
問3 一定の音韻的な環境で交替する例
1 産毛、すね毛、胸毛、まつげなど、「げ」になる規則性がありません。
2 「一」の後ろに子音k、s、t、pが来るとき、「いっ」になります。(一回、一切、一体、一杯…)
3 木霊(こだま)、木陰、木の葉、木漏れ日など、「こ」になる規則性がありません。
4 「ぎょう」と「こう」を分ける規則性はありません。
したがって答えは2です。
問4 擬音語・擬態語に見られる音韻交替
擬音語・擬態語には、音韻交替によって「動作が瞬間的であること」と「動作が滑らかでゆっくりであること」が表せるものが少なくないようです。
「ポロッ:ポロリ」「くるっ:くるり」「ぷすっ:ぷすり」なども音韻交替によって意味の違いが生じています。
したがって答えは3です。
問5 文法的な機能の違いが生まれる音韻交替
音韻交替によって文法的な違いが出るものを選択肢から探します。
ちなみに音韻交替とは、一つの音素が異なる音で現れることです。
選択肢1
他動詞「残す」はヲ格を取ります。「~を残す」
自動詞「残る」はガ格を取ります。「~が残る」
音韻交替によって動詞が変わり、取るべき格助詞も変わりました。
選択肢2
「彼女はさびしがっている」と「彼女はさみしがっている」は同じ意味です。文法的な違いもありません。
選択肢3
「渡す」に音素がいくつも加えられて「渡される」となっているので、そもそも音韻交替って言わないと思うんですが…
「渡す」と「渡る」であれば、この問題の正解となります。
選択肢4
他動詞「とめる」はヲ格を取ります。「~をとめる」
他動詞「やめる」はヲ格を取ります。「~をやめる」
音韻交替によって文法的な違いは生まれないみたい。
したがって答えは1です。

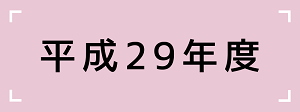
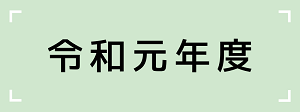




コメント
コメント一覧 (8件)
独学なので、たいへんお世話になっております。ありがとうございます。
問2についてですが、「音韻的に異なる要素」とあるので、
1 [pi] と [bi] 異なる
3 [ha] と [wa] 異なる
4 [o] と [o] 同じ
と判断するのだと思いました。
2は [ha] と [ha] で同じなので最初わからなかったのですが、助詞「が」が付くと、
「歯が」は高低
「葉が」は低高
になるので、そこが音韻的に異なるということかと考えましたが、いかがでしょうか。
>薩摩さん
この問題をもう一度見直してみたのですが、音韻的に異なる要素と言いながら、私は形態素の方面から解説を書いていて変だなと思いました。やはり以前コメントいただいたkouさんの考え方がどうもしっくりきます。
答えは4ですが、なぜ2も正しいと思われたのか教えていただけますでしょうか。
いつも参考にさせていただいています。
ありがとうございます。
問1ー1の自由形態素、拘束形態素の違いなのですが、ごちゃごちゃしてしまって…すみません教えていただければと思います。
選択肢1の髪ですが、「かみ」と訓読みで読んだら単独で使えるので独立形態素、「はつ、ぱつ」と読ませると単独では語として使えない?通常使わない?ので拘束形態素かと思ったのですが…
漢字は読み方に訓音があるものが多く、訓読みの時は単独で語として使えて、音読みをすると独立で使うことがあまりないように思うのですが。
先生の解説や赤本を見ていると、拘束形態素は接頭語接尾語、動詞形容詞の活用部分、その他のものは自由形態素(音訓読みは気にせず)と分ければ良いのかなと思ったのですが、いかがでしょうか?
>noliさん
音読みと訓読みは関係ありません。単独で語になれるかどうかが自由形態素と拘束形態素を分ける境目です。
拘束形態素は接辞だと覚えてください。
接辞は「お電話」の「お」のような接頭辞や、「造語性」の「性」のような接尾辞、それから「食べる」の活用語尾「る」、「食べない」の「ない」なども屈折接辞と言って、これも接辞です。
これらは単独で語になれません。例えば「お電話」の「お」は美化語として丁寧さの度合いを高める機能がありますが、それは「電話」についてやっとその意味を持ちます。ですから「お」は単独で語にはなれないのです。接辞は全て、何か他の語についてやっと意味を持つので、その使用が拘束的、すなわち拘束形態素です。
髪は「かみ」「はつ」「ぱつ」と読めますが、これは接辞ではありませんので自由形態素です。
ちなみに髪の最も一般的な読み方は「かみ」で、これが自由形式です。
「はつ」や「ぱつ」は最も一般的な読み方とは言えないので拘束形式です。
お忙しいところ解説していただき、ありがとうございました。
何時もありがとうございます。
独立形態素と自由形態素について
先生の説明の中で{kin}は、独立形態素となるためには 金にも巾にも菌にもなれるから、とのご説明でした。
私は、金髪の金は、それ自体で語になれるので、独立形態素の自由形式と判断していましたが、それでは間違いなんでしょうか。
また、{kin}が金巾菌になれるというところがよくわかりません。
また、金は、訓読みでかねと読みます。カネ髪とは言わないですね。
この場合は、訓読みでは判断しないのでしょうか。基本的なことですみません。
>塩饅頭さん
単独で現れることができる形態素は自由形式、単独で現れることができない接辞などの拘束形態素は拘束形式と呼んでいます。
例えば「金(きん)」という言葉は、「金」髪、「金」メダル、「金」色など、いろんな要素として自由に現れることができます。
仮に「髪」がなくても「きん」ですし、「メダル」がなくても「きん」ですし、「いろ」がなくても「きん」です。その他の要素の影響を受けず、単独で現れるので自由形態素です。
訓読み「金(かね)」もそうです。「金」持ち、お「金」など。
でも「金(がね)」ならどうでしょう。有り金、筋金など…。これらは「がね」と読みますよね。
仮に「有り」や「筋」がなくて「金」だけの状態だったら、「がね」と読みません。
「がね」と読むのは「有り」や「筋」と一緒に現れているからです。つまり「がね」はその使い方が不自由で単独で現れることができない拘束形式ということになります。
訓読みであるか音読みであるかは関係ありません。
他にも…
「原」という字は、「はら」「わら」「ばら」などの読み方がありますよね。原っぱ、藤原、海原など。
このうち単独で現れることができるのは「はら」だけです。これが自由形式。
それ以外の「わら」や「ばら」はほかの語がないとこのように読みませんので拘束形式です。
簡単に言えば、ある漢字の最も普通の読み方が自由形式で、普通ではない読み方が拘束形式です。
先生、ありがとうございました。
ご丁寧な説明、やっとやっと 理解できました。
去年試験受けはしたのですが、内容を十分理解しているかが問われていたと実感しました。
あと少しで試験ですが、是非合格したいです。