平成25年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題8解説
問1 言語適性
1 「生涯一定」や「見解が一致」などという言いきりの表現は怪しむべきです。
2 その通りです。試験のために勉強するなら記憶力の適正が必要ですが、試験ではなくとにかくコミュニケーション!というなら記憶力よりも音韻処理能力のほうが必要。確かに場面によって必要な適性は異なります。
3 言語適性が高いと、当然習得の速度も速いです。この2つは関係しています。
4 コミュニカティブな授業が好きな人な人もいますし、暗記が好きな人もいますし。それは結局その人の言語適性です。
したがって答えは2です。
問2 動機づけ
行動の原動力となるものや、そのきっかけのことを動機づけといいます。いわゆるモチベーションです。そのモチベーションの源泉が外部なのか内部なのかで分けられます。
| 外発的動機づけ | 外部からの報酬を得るため、罰を回避するための行動の原動力となるもの。 |
|---|---|
| 内発的動機づけ | 自分の内側から湧いてくる行動の原動力となるもの。好奇心や興味によることが多く、長期間持続しやすい。 |
例えば、母親と子供が「歴史のテストで100点取ったらゲーム買ってあげる。80点以下だったらお小遣い減らすよ」と約束し、子どもは歴史の教科書をたくさん読むようになった場面を考えてみます。子供が歴史の教科書を読んでいるのは、ゲームという報酬を得るため、そしてお小遣い減額という罰を回避するためなので、外部要因によって教科書を読んでいることになります(外部的動機づけ)。
逆に「歴史が大好きで子供のころから本をたくさん読んでいた。」という子供がいたとします。この子供が歴史の本を読んでいるのは好きだからです。つまり内部要因によって本を読んでいます(内部的動機づけ)。
第二言語習得においては、ガードナー (Gardner)が道具的動機づけと統合的動機づけを提唱しました。これは外国語を学習するときの動機を分類したものです。
| 統合的動機づけ | その文化に溶け込みたいという気持ちからくる学習のこと。価値観や文化観を理解したい、もっと周囲とコミュニケーションを取りたい、好きなアイドルを追いかけたいなどがこれにあたる。 |
|---|---|
| 道具的動機づけ | お金の為、進学や就職に有利だからという理由で外国語を学習すること。 |
1 道具的動機付け(外発的動機づけ)
2 外発的動機付け
3 統合的動機付け(内発的動機付け)
4 外発的動機付け
したがって答えは1です。
問3 習得開始年齢
外国語環境と第二言語環境の違いについてまず説明します。
外国語環境とは、その言語を外国語として勉強する場合のことで、日本で英語を学ぶ場合がこれ。
第二言語環境とは、その言語が実際に使われている環境に身を置いて自然に身につく場合のこと。長期滞在、移住などがこれ。
選択肢1
臨界期というのは、ある年齢を過ぎたら母語話者のような言語能力を習得するのは難しいとする、その年齢のことです。レネバーグは臨界期仮説で、臨界期は12~13歳頃だと主張しました。でも、特に海外から来て力士になった方たちを見ると母語話者のように日本語を流暢に扱ってますし、臨界期を過ぎても習得はできますよね。
選択肢2
その通りです。実際語彙や文法などの能力は幼児よりも年長者のほうが習得スピードが速いという研究結果があります。それは年長者のほうが既に習得している母語を利用したり、発達した認知能力を利用して第二言語を学ぶことができるからです。ある程度母語が発達しているとスタートダッシュみたいなことができる、つまりカミンズの発達相互依存仮説ですね!
選択肢3
日本の幼稚園で英語を学ぶのと、アメリカの幼稚園で日本語を学ぶのでは、後者のほうが上達が早いのは直感的にも分かると思います。それはインプットの量が比較的できないほど多いことと、コミュニケーションするためにアウトプットが絶対的に必要という点が挙げられます。インプットの量に関係ないわけありません。
選択肢4
発音に関しては早い時期に始めたほうが有利で、語彙や文法については年長者のほうが早く習得できるようです。文法と音声の臨界期は異なります。
したがって答えは2です。
参考:「英語は小さい頃に始めた方がいい」という誤解 | 英語学習 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準
問4 ビリーフ
学習者の要因として、言語適性、動機づけ、習得開始年齢が挙げられてます。選択肢の中から学習者の要因であるものを探せばいいのですが…
まず選びたいのはビリーフ。これはまあまあ出てくる言葉なので、出題傾向が分かっている人なら真っ先にこれを選ぶはずです。ビリーフはどのようにすれば言語を習得できるかという考え方、信念のことで、学習者の要因です。
それから、パラメータってのもちょっとよく分からないんで飛ばしたいところ。
やっぱり「知能」でしょう。知能は人によって違いますから、ア、イに入れるものとして良いです。
したがって答えは3です。
問5 情意フィルター仮説
1 根本的相違仮説
幼い子どもが言葉を覚えるメカニズムと、大人が第二言語を習得するメカニズムは根本的違うものであるとする仮説。大人が第二言語を習得する際には大きな個人差があるものの、子どもにはあまり差が見られない。
2 インターアクション仮説
ロング (Long)が提唱した、学習者が目標言語を使って母語話者とやり取り(インターアクション)する場面で生じる意味交渉が言語習得をより促進させるという仮説です。意味交渉はインターアクションの中で生じる意思疎通の問題を取り除くために使われるストラテジーで、以下の3つに分けられます。
| 明確化要求 | 相手の発話が曖昧で理解できないときに、発言を明確にするよう要求すること。 |
|---|---|
| 確認チェック | 相手の発話を自分が正しく理解しているかどうか確認すること。 |
| 理解チェック | 自分の発話を相手が正しく理解しているかどうか確認すること。 |
3 敷居仮説
カミンズ (Cummins)によって提唱された、バイリンガルの程度と認知との関係性をまとめた仮説のこと。二言語を年齢相応の母語話者レベルで使用できる均衡バイリンガルの場合は認知上プラスの影響を与え、両言語とも十分なレベルにまで達していない限定的バイリンガルの場合は認知上マイナスの影響を与えるとされる。その中間に位置する、二言語のうち一方のみが年齢相応のレベルまで達している偏重バイリンガルの場合は、モノリンガルと同様、認知上プラスにもマイナスにもならないとされている。
4 情意フィルター仮説
学習者の言語に対する自信、不安、態度などの情意面での要因がフィルターを作り、接触するインプットの量と吸収するインプットの量を左右するという仮説。モニターモデルを構成する仮説の一つ。
「不安度が高いと習得を阻害する」が情意フィルター仮説と同じ内容です。
したがって答えは4です。

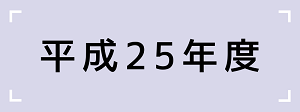
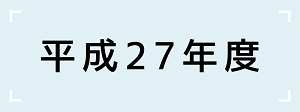

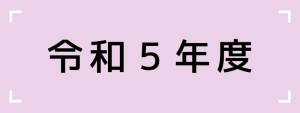



コメント
コメント一覧 (2件)
平成25年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題8 問2の解説ですが、選択肢1について、「(内発的動機づけ)」となっていますが、「(外発的動機づけ)」ではないかと思います。ご確認をお願いします。
>にんじんさん
確認しましたところ誤りがありました。コメント頂いた通り「外発的動機づけ」です。ご指摘ありがとうございました!