平成25年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題7解説
問1 JFLとJSL
| JFL(Japanese as a Foreign Language) | 外国語としての日本語のこと。 |
|---|---|
| JSL(Japanese as a Second Language) | 第二言語としての日本語のこと。 |
「F」はfirstかな?って予想しちゃうと「第一言語」を探しちゃうので選択肢1を選んでしまいます。「F」はForeignですから間違えて覚えないようにしてください!
選択肢4には「外国語として」と「第二の言語として」というヒントがあります。
したがって答えは4です。
問2 JGP
| JGP(Japanese for General Purposes) | 日常生活で用いられる一般的な日本語のこと。 |
|---|---|
| JSP(Japanese for Specific Purposes) | 仕事や研究などの特定の目的に用いられる特別な日本語のこと。 |
この2つは日常で用いる日本なのか、特定の場面で用いる日本語なのかで分かれます。
1 「簡単な読み書き」とありますので専門的ではありません。JGPです。
2 接客業で使う日本語は仕事で用いる特別な言葉なので、JSPです。
3 運転免許取得のために日本語は特別な言葉なので、JSPです。
4 論文の書き方についての日本語は特別な言葉なので、JSPです。
したがって答えは1です。
問3 JSP
1 否定する部分がない気がするんですが… 学習計画も授業も教師がやれってことでしょうか。
2 免許取りたいという学習者にそれ関係の日本語を教えるとき、もちろん運転免許のことを知っている教師がいると良いですし、運転免許センターに勤めてたり、あるいはそっち方面に詳しい関係者が手伝ってくれるともっと良いです。この選択肢は正しいです。
3 特定の場面で使う日本語(JSP)はその学習者がどうしても必要だから学んでいるわけで、ということは産出を優先したほうがいいです。
4 意味分かんないです。
答えは2です。
問4 特殊環境下での海外帰国児童生徒の日本語能力
小学校低学年以前は日本にいて海外渡航後も家庭で日本語を使っているとのことなので、発音については問題ないと推測できます。成人に比べ、子どもは音声を正確に習得できます。選択肢1は間違い。
それから小学校低学年くらいであれば動詞の活用、接続は年齢相応の母語話者レベルであると推測できます。選択肢2も間違いです。
それから家庭でしか日本語を使ってこなかったので普通体のほうがよく使っているはず。丁寧体が苦手になりやすいです。選択肢3も間違い。
この子どもは読み書きをする環境にいなかったので、文章の読み書きは苦手だと思われます。
したがって答えは2です。
問5 日本での就職を考えている留学生対象のビジネス日本語教育
1 日本で仕事をするための能力は絶対必要。
2 必要です。母国と日本の仕事のやり方、考え方は違うので、そういう面を知っておくことは就職に役立ちます。
3 「日本で就職を考えている」とだけありますので、「ある特定の業種に必要な日本語」を教えるのは間違いです。
4 必要です。対面だけでなく、電話やメールを扱う仕事もありますので。
したがって答えは3です。

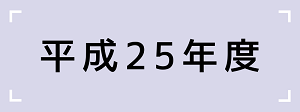

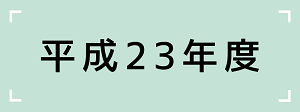
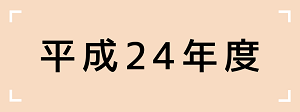

コメント
コメント一覧 (1件)
問3についてです。
選択肢1は、例えば、コンピューターのことについて学びたい学習者に対し、専門分野の教師、つまりコンピューターの教師が学習計画を管理しなければならない、という意味ではないでしょうか? 日本語教師ではなく。各分野に日本語教師はいませんよね。だから正解は2の日本語教師が、コンピューター関連の教師や関係者と連携していく、という事だと思います。