平成24年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題7解説
問1 シラバス
「~です」「~ます」「~ました」「イ形+かった」「~ている」などと、文型を簡単な順から扱っている、典型的な構造シラバスの例です。後半になると「~前に」「~てから」「~ために」「~しなければならない」などとおよそ初級の終わりから中級の始まりくらいに扱うような表現が含まれています。
構造シラバスで初級から中級くらいのレベルです。
したがって答えは4です。
問2 質問項目
1 受け身の「~される」、時間の「~とき」などはこの段階では早すぎ。中級はじめくらいのレベルなので位置的には12前後のあたりにあるのが適当です。
2 「いつも何時に起きますか」は3の前後辺りにあるのが適当。簡単すぎます。
3 意向形「~よう」、引用「~と思う」などはまだまだ早い。12の前後あたりにあるのが適当だと思います。
4 5でテ形は入っているのでタ形も使えます。「~たことがあります」はこの段階で十分扱えます。
したがって答えは4です。
問3 <方法A>の改善案
選択肢1について、「はい」「いいえ」だけで答えられるような質問は簡単すぎますし、「Aですか?Bですか?」のような選択疑問文も、選択肢が限られているので簡単すぎます。これが不適当です。
答えは1です。
問4 <方法B>のクラス
<方法B>では、できるかできないかの項目が並べられています。学習言語を使って目標を達成できるかどうかを測定するのに役立ち、その能力に応じたクラス編成をする場合に適当です。
答えは3です。
問5 評価項目としてふさわしくないもの
1 名前や出身などは最低限の自己紹介なのでプライバシーの侵害まではいきません。不適当です。
2 確かに休憩中に誰と話すか、何を話すかによって難易度が変わります。この項目を設定しているのはふさわしくないです。
3 いつどこで会うかの約束が易しすぎるということはなくて、初級終わりか中級はじめくらいの能力が必要です。これは不適当。
4 注文したものが出てこなくて苦情を言うことは正当な理由というか、逆に言うべきで不利益になったりはしません。これも不適当。
答えは2です。

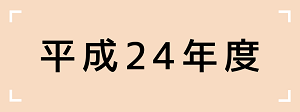


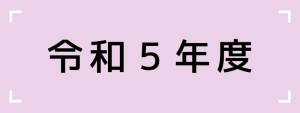
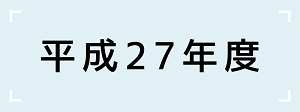
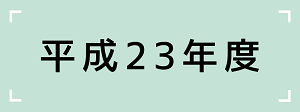
コメント