平成23年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題2解説
問1 実質語
内容語(実質語)と機能語の違いについての問題です。
内容語というのは、名詞、形容詞、動詞などの実質的な内容や意味を表す語のことです。
機能語は代名詞、接続詞、助動詞などの文法的な役割や話し手の事態の捉え方を表す語のことです。
選択肢1
実質語には日常で使うようなものもありますし、専門的な場面で使うものもありますし、幅は広いです。
子どもだと比較的簡単な言葉中心に使いますが、大人になると語彙も増えて難しいのも使えるようになりますので、当然個人差はあります。
選択肢2
実質語は、鳥、速い、飛ぶみたいに和語もありますが、鳥類、高速、飛行みたいな漢語もあります。バード、スピード、フライと外来語もあります。和語の割合が多いとは言えなさそう。
でも機能語はそのほとんどが和語だと言われています。例えば「~かもしれない」「しかし」「~にとって」「~だけど」みたいに、大体和語が思い浮かびます。
選択肢3
学齢期とはおよそ15歳を指しますが、この年齢までにほとんど全ての語彙を覚えるかと言えばそうではありません。その年齢以後も語彙は増えていきますね。
選択肢4
実質語は「こどおじ」のように、語同士を組み合わせたりして新しい語を容易に作れます。造語性が高いんですね。
でも機能語はなかなか新しい語を作ることはできません。
したがって答えは1です。
問2 シンタグマティック
パラディグマティックな関係とシンタグマティックな関係という言葉が出てきてます。
パラディグマティックについては文章中で説明がありますね。それは「運転する」「操縦する」「漕ぐ」などの範列的な関係だそうです。つまりこんな感じ。
AがBを運転する
AがBを操縦する
AがBを漕ぐ
これが縦に並んでいるように見えるので、縦の関係とも呼ばれたりします。
もう一つはシンタグマティックな関係です。文章中にヒントになるようなものはあまり無いんですが… これは「眼鏡」と「かける」、「水」と「かける」みたいに、文として直線的に並べられる言葉の関係のことです。横の関係とも呼ばれたりします。
ここでは「漕ぐ」とシンタグマティックな関係に位置する語を聞いてますので、答えは「自転車」です。「自転車を漕ぐ」と言えるからです。
したがって答えは2です。
問3 一連の語を体系として提示する
選択肢1
文章中であるように、パラディグマティックやシンタグマティックな関係にある語、対義語、類義語などを同時に提示することによって、体系的に語彙を学ぶことができるようになります。これらを既習語のみで行うことは不可能です。
選択肢2
正しいです。その学習者が必要な言葉、比較的使用頻度が高そうな言葉から教えていくのは良いこと!
選択肢3
「登る」と「下りる」は対義語の関係にありますが、「山に登る」と「山を下りる」のように、格関係が同じではないものもあります。
選択肢4
ここでいうコロケーションとは、「辞書」と「引く」、「風邪」と「引く」みたいな言葉の自然の組み合わせのことです。このような共起する頻度が高い語は一緒に教えたほうが効率的ですが、できる限り全て導入する必要もありません。必要なものだけ教えたほうがいいです。
したがって答えは2です。
問4 慣用句
慣用句とは、2語以上の単語が固く結びつき、全く異なる意味を持つようになったもののことです。例えば「目がない」はその語が持つ意味を失って、「我を忘れるほど好きな様子」を表すようになってます。こういう感じのが慣用句。
選択肢1
正しいです。「目がない」を「目がとてもない」とは言いにくいのは、「目がない」で一つの言葉として捉えやすいからだと思います。だから副詞が入り込む隙が無くなっているんですね。
選択肢2
正しいです。「打つ」と「叩く」は類義語ですが、「相槌を打つ」とは言えても、「相槌を叩く」とは言いにくいです。
選択肢3
正しいです。上述の通り。
選択肢4
間違いです。「相槌を打つ」と言うようになったのは師匠と弟子が交互の槌を打つことを「相槌」と呼んでいて、それが転じて今の相づちの意味になっています。こういう文化的背景から作られた言葉はその文化でのみ通じる表現なので、言語間で共通するということはなかなかありません。
したがって答えは4です。
問5 格成分
| 1 | ~が~を作る | ~が~を焼く | ~が~を~に加える |
|---|---|---|---|
| 2 | ~が~に触れる | ~が~を壊す | ~が~にぶつかる |
| 3 | ~が~と結婚する | ~が~とけんかする | ~が~を説明する |
| 4 | ~が~を~に見せる | ~が~を~に貸す | ~が~を~に渡す |
各動詞の取る格を並べると、選択肢4だけ全て一致しています。
したがって答えは4です。
問6 語彙指導
選択肢1
語彙を指導する際は、その意味と漢字、発音を同時に教えるべきです。
選択肢2
正しいです。例えば何か本を読んでいて分からない語に当たったとき、そこで諦めたり、やる気をなくしたりする人がいます。そういう時はスマホで調べてとか、先生に聞いてとか、友達に聞いてみてとか、自律的な学習を促せるような指導はしたほうがいいに決まってます。
選択肢3
知っている実質語なら母語を介して理解できます。知らない実質語でも、その意味は前後の文脈などからも推測しやすいです。だから全部が全部訳がいるかというとそうではありません。推測しにくい未習のもの、レベルが高いものは訳を付けたほうがいいですね。
選択肢4
例えば「~せいだ」は悪い原因を表す言い方です。母語話者であれば「~せいだ」はなんかマイナスのニュアンスがあるなーとすぐ分かります。教師によって異なるということもまずありえません。ですからこういうニュアンスやイメージについては説明したほうがいいです。
したがって答えは2です。

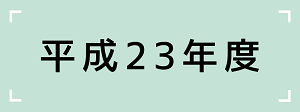


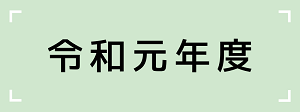
コメント