平成29年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題9解説
問1 行動主義心理学に基づく言語習得観
選択肢1
中間言語の説明。中間言語とは、第二言語学習過程における発展途上にある言語体系のこと。母語の影響を受けながらも、徐々に目標言語に近づいていくものとされる。セリンカーが提唱した概念。
選択肢2
行動主義心理学の行動主義学習理論では、学習は刺激に対する反応を繰り返すことによって習慣的に形成されると考えられています。この理論に基づいてオーディオ・リンガル・メソッドが開発されました。
選択肢3
スキャフォールディングの説明。スキャフォールディング(足場掛け)とは、ヴィゴツキー (L.S.Vygotsky)が提唱した最近接発達領域/発達の最近接領域(ZPD)において、「できる」と「できない」の中間的な段階で周囲の大人が行う様々なアドバイスやサポートなどの支援のことです。
選択肢4
これはモニターモデルを構成する5つの仮説のうちの一つ、情意フィルター仮説です。学習者の言語に対する自信、不安、態度などの情意面での要因がフィルターを作り、接触するインプットの量と吸収するインプットの量を左右するという仮説です。
したがって答えは2です。
問2 対照分析仮説
1 根本的相違仮説
幼い子どもが言葉を覚えるメカニズムと、大人が第二言語を習得するメカニズムは根本的違うものであるとする仮説。大人が第二言語を習得する際には大きな個人差があるものの、子どもにはあまり差が見られない。
2 分離基底言語能力モデル
カミンズによって提唱されたバイリンガルの言語能力についての仮説。脳内には2つの風船(言語)があり、一方が膨らむと一方が縮んでしまうように、言語も一方が強くなるともう一方は弱くなるとする考え方のこと。

3 創造的構築仮説
学習者が第二言語を習得する際には、母語とは独立した新しい言語体系を作り上げていくという仮説。言語体系は0から新しく作り上げられると考えられているため、母語による影響はほぼないとされている。
4 対照分析仮説
母語と第二言語の言語間の類似点・相違点を比較することによって、学習の難易度や誤りを予測することができるとする仮説のこと。つまり類似点が多ければ学習は容易になり、相違点が多いと困難になるとし、その相違点に焦点を当てることで学習が効率的になると考える。
下線部Bは対照分析仮説の考え方です。
したがって答えは4です。
問3 誤り
学習者の誤用は、つい間違えてしまったというタイプのミステイクと、言語能力が不足していることによって起きるエラーに分けられます。エラーはさらに以下に分けられます。
| 程度 | グローバルエラー全体的な誤り | コミュニケーションに大きな支障が出るエラーのこと。「これはAさんにもらったプレゼントです」が「これはAさんがもらったプレゼントです」になるようなエラー。 |
|---|---|---|
| ローカルエラー局部的な誤り | コミュニケーションに影響が少ないエラーのこと。「私は学校で勉強をします」が「私は学校に勉強をします」になるようなエラー。 | |
| 原因 | 言語間エラー言語間の誤り | 母語による影響で生じた誤りのこと。中国語母語話者が「宿題をします」を「宿題を書きます」と言ったり、「薬を食べます」と言う等。 |
| 言語内エラー言語内の誤り | 母語とは関係なく、第二言語の学習の不完全さから生じた誤りのこと。「雨が降りました」と「雨を降りました」と言う。言語内エラーには過剰般化や簡略化などがある。 |
選択肢1
過剰般化とは、文法的な規則を他のところにも過剰に適用することによって起きる言語内エラーの一種です。例えば「安くはありません」を「安いではありません」と言うようなこと。
過剰般化で生じた誤りは言語間の誤りではなく、言語内の誤りです。
選択肢2
母語干渉によるエラーは言語間エラーです。母語が関係してるので。
選択肢3
正しいです! 理解をきたすのはグローバルエラーですね。
選択肢4
教師による不適切な指導が原因で生じる学習者のエラーは訓練上の転移と呼びます。
したがって答えは3です。
問4 誤用分析研究
選択肢1
誤用分析研究は学習者の誤用を分析して指導に生かそうとするもので、言語習得の全体像を捉えることは難しいです。
選択肢2
学習者を観察して得られた誤用を分析するため、それが一時的な言い間違え(ミステイク)なのか、系統的な誤用(エラー)なのかを区別するのは第三者にとって難しいことです。
選択肢3
選択肢2と同様、誤用分析研究は学習者を観察して得られた誤用を分析するため、使用が回避された(言われなかった)ものはデータとして取ることができません。
選択肢4
誤用を分析するためには多くの学習者の誤用を集める必要があり、一人を継続的に観察する縦断的観察は適切とは言えません。集団に対して横断的観察を行えばデータ数が多く得られます。
したがって答えは4です。
問5 自然習得順序仮説
自然習得順序仮説はクラッシェンが提唱したモニターモデルを構成する仮説の一つです。目標言語の文法規則はある一定の決まった順序で習得され、その自然な順序は教える順序とは関係ないと考えられています。
1 分かりません! 誰か教えてください。 有標のものを学ぶとより簡単な無標も習得できるような気がしますが、いずれにしてもこれは自然習得順序仮説の説明ではありません。
2 自然習得順序仮説の説明です。
3 これも分かりません!
4 これは自然習得順序仮説に近いようですが、「教室環境では」という部分が余計です。
したがって答えは2です。

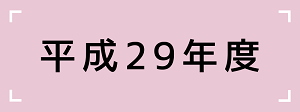
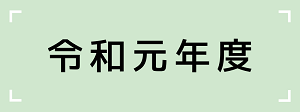




コメント
コメント一覧 (1件)
こんにちは。検定試験に備えて高橋さんの解説を大変有り難く使わせ頂いて頂いている者です。有難うございます。
問題5の選択肢1)はZoblの「投射モデルProjection model(学習者には投射装置があって、規則を一つ習得すればそれに関連する他の規則の習得までも引き起こす。→有標の規則を習得すれば、無標のものもインプットにより自然に習得できる」ではないかと思います(間違っていたらすみません)。