目次
平成27年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題2解説
問1 「なければならない」と「べき」
1 「なければいけない」も「べき」も、規則や常識などに基づいて必要であることを表します。
2 「なければいけない」は意志動詞にも無意志動詞にも接続できますが、「べき」は意志動詞にしか接続できません。
3 正しいです。
4 「なければならない」は否定形がなく、「べき」は否定形「べきではない」があります。
したがって答えは3です。
問2 東京に来たら私の家に来たほうがいいです
1 正しいです。
2 「ほうがいい」が表す対象の動作には、話し手の肯定的な評価が含まれます。
3 目上から目下、目下から目上、どちらも使うことができます。
4 「東京に来たら、◯◯に遊びに行ったほうが良い」と、条件文でも使用できます。
したがって答えは1です。
問3 過去形のときの意味
「べき」「ほうがいい」の過去形は「べきだった」「ほうがよかった」です。過去形ではいずれも、話し手の物事が発生しなかったことに対する後悔を表せます。
したがって答えは2です。
問4 モダリティ形式
1 勧め 「~たらいい」
2 不必要 「~までもない」
3 必要・義務 「~ざるをえない」
4 意志 「~つもり」
したがって答えは4です。
問5 「なければならない」と「なければいけない」
1 「なければならないです」「なければいけないです」と、どちらも丁寧体にできます。
2 「なきゃならない」より「なきゃいけない」のほうがよく使われます。
3 正しいです。
4 「なければならない」は書き言葉的で、「なければいけない」は話し言葉的です。
したがって答えは3です。

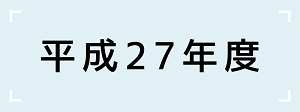

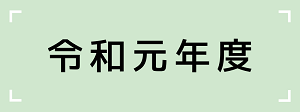
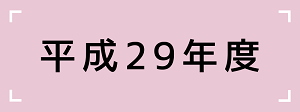

コメント
コメント一覧 (8件)
すみませんが、問5の解答は3となっていますが、 話し言葉の時に、「なんなきゃならない」をよく使うと考えるのですが。これは北海道の特徴で他地域では「いけない」なのでしょうか?
お手数おかけいたしますが、返答頂ければ幸いです。
>晴山さん
コメントありがとうございます! 問5についてお答えします。
選択肢4の解説でもありますが、標準語における「なければならない」は書き言葉的で、「なければいけない」は話し言葉的です。例えば「てしまう」の縮約形「ちゃう/じゃう」なども書き言葉では現れにくいように、縮約形が話し言葉で現れやすいというのは縮約形全般に言えることです。よって「なきゃならない」よりも「なきゃいけない」のほうがよく使われると考える方が自然です。
「なんなきゃならない/なんなきゃなんない」は「ならなければならない」の縮約形ですが、おっしゃる通り、後者は話し言葉でもよく使われる気がしますね…。ここからは推測ですが、「なんなきゃならない」の「な」と「ら」はいずれも歯茎を調音点として発音しますので、全体を通して舌をあまり動かす必要がなくなり、「いけない」よりも言いやすくなるのだろうと思います。言いやすくなるというのも縮約形の特徴ですので、話し言葉で用いられる頻度が高くなっているのかもしれません…。
とはいっても、「なきゃならない/なきゃならん」と「なきゃいけない/なきゃいかん/なきゃいけん」などは確かに地域差がある気がします。地域差があるとそれが標準語であるという扱いがしにくくなりますので、やはり”縮約形は話し言葉に現れやすい”という標準語の原則を用いて解き進めるほうがいいと思います。
詳しい解説をしてくださりありがとうございます。とても、よく理解出来ました。北海道特有なのか余り「なければいけない」という言葉を聞く機会が少ないような気がします。「なければなんないしょ」という北海道弁的な使い方もよく耳にします。こういう問題があった時は標準語を調べるようにします。本当にありがとうございました。
問5の「〜ならない」と「〜いけない」、私も、どちらも話し言葉で使えると思い、迷いました。
そこで思いついたのが「なければ」の部分を「ねば」に置き換えてみることです。
この「ねば」に続けてみると、「ねばならない」には違和感はありませんが、「ねばいけない」には不自然さを感じます。
「ねば」は「なければ」に比べて硬い表現で、話し言葉で使うこともありますが、それは講義や演説などがほとんどで、書き言葉寄りの表現だと思います。
このことから考えて「なければならない」は書き言葉的ニュアンスを、「なければいけない」は話し言葉ニュアンスを持つと判断するのはどうでしょうか。
>kouさん
そのように説明すると分かりやすいですね!
貴重なご意見ありがとうございました。
初めて質問させてきただきます。
基本的な語彙の意味についてで申し訳ないのですが、問2-1について教えていただければと思う。
選択肢4に肯定形と否定形の対立がある、とありますが、〜と〜の対立とはどういうことなのでしょうか?過去問を見ていると時々この対立という言葉が出てきて、毎回どうしても理解ができません。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>noliさん
こんにちは! コメントありがとうございます。
「『なければならない』は肯定と否定の対立があるのに対し、『べきだ』は対立がない。」のことですね。
対立とは、ある観点から見て2つのものが対応していることです。
肯定形と否定形という観点から見ると、「べきだ」は肯定形、「べきではない」は否定形です。この2つが対応しているので、”対立している”と言います。
他にも、「自他の対立」という言葉もあります。例えば「落ちる」は自動詞、「落とす」は他動詞です。この2つも対立しています。
さらに「音声的対立」もあります。バ行は[b]有声両唇破裂音、パ行は[p]無声両唇破裂音です。一つは有声音、もう一つは無声音なので、この2つは声帯振動の面から対立しています。
大体このような感じです。共通点はありますが、一部分異なる点があるときに「対立」という語が使われます。
お忙しいところ解説いただきありがとうございました。
今まで分からなかった点がやっと理解できました。
ありがとうございます。
質問の際に変換ミスをしてしまい、「思います」が「思う」になっていました。大変申し訳ありませんでした。