平成23年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題13解説
問1 情報機器を用いても、半数以上の人が仮名表記にする漢字
手書きの場合に漢字で表記すると答えた人が1割未満であった「顰蹙」(4.6%),「齟齬」(5.6%)は,パソコン・ワープロ等を使って選ぶ場合は,漢字で表記する割合が23~24ポイント高くなっている。それでも,半数以上の人が,平仮名で「ひんしゅく」(58.5%)「そご」(52.7%)と表記すると答えている。
- 平成16年度「国語に関する世論調査」の結果について | 文化庁より
したがって答えは1です。
問2 情報機器の普及
「本の形になっている辞書」は,年齢が高くなるとともに割合が高くなり,50代以上では約7割となっている。「電子辞書」は,16~19歳で特に高い(5割近く)。「インターネット上の辞書」は,30代で最も高い(2割強)。「携帯電話の漢字変換」は20代で特に高い(約8割)。ワープロ,パソコンの漢字変換は,30代,40代で高い(3割台半ば)。
- 平成18年度「国語に関する世論調査」の結果について | 文化庁より
したがって答えは3です。
問3 顔文字・絵文字
1 顔文字はそのままで使うか、文末で使うケースのほうが多いです。
2 正しいです。良い印象も与えられますし、場面によっては効果的に感情も伝えられますし。
3 同じ意味を表す顔文字でも、その形には違いがあります。「(^^)」は以前日本でよく見られましたが、欧米では「:D」などを用いるようです。
4 絵文字も顔文字の女性のほうが多く使います。
したがって答えは2です。
問4 ノンバーバル化
初めに言いますが、答えは4です。このコンテクスト化について説明します。
(1) 暖房つけてくれませんか。
(2) 窓を閉めてくれませんか。
(3) この部屋ちょっと寒いですね。
例文(1)(2)は直接的な依頼表現で、(3)は間接的です。直接言ってくれればその場面に依存することなく誰でも依頼されているんだと分かるんですが、(3)のような間接的な言い方だとそれが確かに依頼しているのか、ただ自分の感覚を述べているだけなのかははっきりしません。この間接的な発話が実は依頼であると解釈する(させる)ためには、話し手と聞き手の共通認識、共通概念、コンテクストを形成しておく必要があります。話し手と聞き手が同時にその場にいて、同様に部屋が寒いなーと感じていればそれは共通概念の生成に繋がり、間接的な言い方でもより本来の意図が伝わりやすくなります。
このように話し手と聞き手が影響し合って、その場でのやり取りから新しいコンテクストを形成していくこと、またはそれまでのコンテクストを補強していく過程をコンテクスト化と呼びます。
文章中には「声の抑揚や顔の表情」とあります。怒った表情や低めの声で「なんでもない」というのと、軽やかな感じで微笑みながら「なんでもない」というのじゃ解釈が全然変わります。相手の声の抑揚や表情、態度などから怒っているんだと分かれば、それ以降の会話の解釈も変わります。何気ない身体動作やパラ言語にもコンテクスト化の役割があるということです。
したがって答えは4です。
問5 顔文字・絵文字の機能
文字だけだとなかなか感情は伝えにくいです。適切な場面で適切な顔文字、絵文字、ステッカーなど使えたら自分の感情を正しく表出できますし、相手の感情の理解にも役立ちます。
これらは確かにコミュニケーションにおける誤解や摩擦を回避する役割があるといえます。
したがって答えは1です。

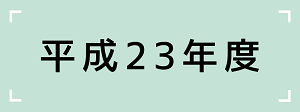

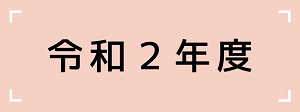


コメント
コメント一覧 (2件)
問4の解答はコンテクスト化なので
解説が間違っています。
>pontaさん
ご指摘ありがとうございます。解説修正いたしました。
pontaさんは平成23年度の過去問をお持ちなんですね! とても珍しいのでびっくりしました。