換喩(metonymy:メトニミー)
換喩(metonymy:メトニミー)とは、2つの概念(喩えるものと喩えられるもの)の隣接関係、もしくはその隣接性(contiguity)に基づき一方の概念を表す形式でもう一方の概念を表す比喩のことです。2つの概念の隣接関係には空間的なものもあれば空間的なものなど様々です。
(1) テーブルを片付ける。
(2) 前の車は運転が荒い。
(3) 米津玄師を聴いた。
(1)における「テーブル」が字義通りの意味なら<テーブルそのものを移動させる>ことを表しますが、文脈によっては<テーブルの上のものを移動させる>ことを表す場合もあります。後者は「テーブル」が「テーブルの上のもの」を指しており字義通りの意味を表していない点で比喩であり、かつ「テーブル」と「テーブルの上のもの」は空間的に隣接していることから換喩(メトニミー)ということになります。(2)も同様に、「前の車」でそれに空間的に隣接している「前の車の運転手」を指しています。(3)は「米津玄師」で「米津玄師が作った曲」を指しています。空間隣接でも時間隣接でもないですが、作者と作品という隣接関係に基づいています。このように換喩(メトニミー)の隣接関係は広く考えて捉えなければいけませんが、換喩(メトニミー)は総じて指し示すものをずらすという特徴を持っていると言えます。

換喩(メトニミー)は、喩えるものと喩えられるものが外接している関係にあるものをトポニミー(toponymy)、喩えるものと喩えられるものが全体と部分の関係にあるものをパートニミー(partonymy)と呼んで区別することがあります。パートニミーは「トイレをノックする」、「手を貸してほしい」などで、「トイレ」でトイレという空間にある「トイレの個室ドア」を指し、「手」でその手を持つ「人」を指しています。全体と部分のうち、全体が喩えるほうになる場合もあれば喩えられるほうになる場合もあります。
空間的な隣接関係
(4) 黒板を消す。
(5) 猫をなでる。
(6) 瓶を飲み干す。
(7) お風呂が沸いた。
空間的な隣接関係に基づく換喩(メトニミー)は喩えるものと喩えられるものが物理的に隣り合っています。(4)の「黒板」は物理的に隣り合う「黒板に書かれた字」を指し、(5)の「猫」も物理的に隣り合う「猫の頭」を指します。(6)(7)のように「瓶」で「瓶の中身」、「お風呂」で「お風呂の浴槽の水」などと容器で中身を表すようなものもあります。
時間的な隣接関係
(8) ベッドに行く。
(9) ガソスタに行ってくる。
(8)「ベッドに行く」はベッドに行ったあとに行われる行為「寝る」を指し、(9)「ガソスタに行ってくる」もその後に行われる「給油する」を指しています。時間的に隣接関係に基づく換喩(メトニミー)は、2つの出来事のうち、片方の出来事でもう片方の出来事を指します。
(10) 甲子園の砂を持ち帰った。 <結果>で<原因>を表す
(11) あくびが出る。 <結果>で<原因>を表す
(12) 涙を流す。 <結果>で<原因>を表す
2つの出来事が時間的に隣接している場合、その2つの出来事には因果関係が認められることがあります。例えば(10)においては、甲子園の全国大会の試合で負けたから甲子園の砂を持ち帰るという因果関係において、結果<甲子園の砂を持ち帰った>で原因<試合に負けた>を表しています。同様に(11)は結果<あくびが出る>で原因<眠い>を、(12)は結果<涙を流す>で原因<悲しい>を指します。
(13) 口がかたい。 <原因>で<結果>を表す
(14) 耳に残る。 <原因>で<結果>を表す
(15) 腰が重い。 <原因>で<結果>を表す
(10)は口がかたいから秘密を漏らさないのであり、原因<口がかたい>で結果<秘密を漏らさない>を表している例。(14)は耳に残るから忘れられない、(15)は腰が重いから行動に移らないわけだから、<原因>で<結果>を表すタイプの換喩(メトニミー)です。
モノとコトの関係
(16) シャンプーがめんどくさい。
(17) 論文が終わった。
(18) ビリヤードが好きです。
(16)は「シャンプー」という<モノ>でシャンプーを使ってする行為「髪を洗う」という<コト>を指しています。(17)も「論文」という<モノ>で「論文を執筆する」という<コト>を指しています。
作者と作品、生産者と製品の関係
(19) 私はBMWに乗っています。
(20) モーツァルトを聴く。
(21) バンドの「ずっと真夜中でいいのに。」が好きです。
(19)は「BMW」で「BMWが作った車」を、(20)は「モーツァルト」で「モーツァルトが作った曲」を指しています。作者と作品、生産者と製品といった隣接関係に基づく換喩(メトニミー)もあります。
その他の隣接関係
上記の隣接関係のいずれにも分類されないものをその他としてここにまとめることにしました。
(22) 3.11を忘れるな
(23) 福島は原発政策を見直すきっかけになった。
(24) 永田町の常識
(25) 金閣寺は足利義満によって建てられた。
(22)は時間「3.11」とその出来事「東日本大震災」、(23)は場所「福島」と出来事「原発事故」、(24)は場所「永田町」と機関「国会」という隣接関係に基づく換喩(メトニミー)です。(25)において、実際に金閣寺を建てたのは足利義満ではなく、足利義満によって命令を下された職人です。この2者にも「命令する人」と「命令される人」という隣接関係が認められます。なお、(2)は「命令する人」と「命令される人」の隣接関係として見るほうがより正確かもしれません。
(26) 私の10万円が! (10万円で買った自転車が盗まれて)
(27) ここで彼女を待ちます。 (※これは自信がないけど…)
本では見かけなかったけど、(26)のように物とその金額の隣接関係に基づいた換喩もありそう。
(27)は確信はないけど「彼女」で「彼女が来る」を指していて、人でその人の行動を指していると見れそうなので一応書いておきました。
参考文献
認知言語学なら、↑がおすすめ!はじめてでも分かりやすい。
谷口一美(2006)『学びのエクササイズ 認知言語学』59-65頁.ひつじ書房
辻幸夫(2003)『認知言語学への招待(シリーズ認知言語学入門(第1巻))』140-168頁.大修館書店
籾山洋介(2010)『認知言語学入門』44-52頁.研究社
吉村公宏(2004)『はじめての認知言語学』103-116頁.研究社



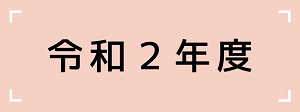


コメント