平成30年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題6解説
問1 帰納的アプローチ
帰納的アプローチ、演繹的アプローチについてしっかり覚えておきましょう! この2つ混乱しないように。
| 帰納的アプローチ | 学習者に用例を示して、学習者自身が用例の中から文法規則を見つけ出させるアプローチをとります。ポイントは学習者自身に気づかせること。 |
|---|---|
| 演繹的アプローチ | 教師が先に文法規則を明示的に教えるアプローチ。学習者自身に気づかせるのではなく、最初から規則を教えちゃいます。 |
選択肢1
文法規則を指導するのは演繹的アプローチです。この選択肢は間違い。
選択肢2
教師が提示した例文から学習者に規則を見つけ出させるのは帰納的アプローチです。しかし帰納的アプローチで提示される例文は教師がちゃんと選別したものを使います。無作為に選んだ例文を使うと例文に含まれる語彙とかがレベルに合わなかったりするので良くないです。この選択肢は惜しい。
選択肢3
「文法規則の発見」
まさに帰納的アプローチの特徴です。これが答え。
選択肢4
文法説明を好むタイプの学習者には、文法説明をする演繹的アプローチを行うべきです。
したがって答えは3です。
問2 初級における媒介語の使用
言語教育において、学習者の目標言語ではない言語で教えるようなとき、その言語を媒介語と言います。例えば、日本語の授業で一部英語で説明するような場面もあると思いますが、このときの英語が媒介語。媒介語は使い過ぎると学習者がそれに慣れてしまって悪い影響が出たりします。かといって複雑なことを日本語ばかりで説明しても伝わらないので、ここぞというときに媒介語は必要になることもあります。
選択肢1
説明が難しくて目標言語での説明がかえって時間を費やすようであれば、媒介語を使ってスムーズに説明したほうが良い場合もあります。これは正しい。
選択肢2
その通りです。媒介語を使いすぎると媒介語使ってもいいんだーみたいな空気になるので、目標言語を使ってくれなくなったりします。依存させると良いことありません。
選択肢3
教室でよく使用する表現、例えば「立ってください」「これは何ですか?」などの教室用語は目標言語を用いるべきです。この選択肢は間違い。
選択肢4
その通り。社会的な話、文化的な話は目標言語で説明すると長くなっちゃうし、内容も難しい。だったら理解優先で媒介語使ったほうがいいです。例えばどうして刺青があると温泉に入れないの?みたいな文化的な問題は媒介語で説明してしまったほうがいいでしょうね。
答えは3です。
問3 オーディオリンガル・メソッドの文型練習
オーディオリンガル・メソッドはとにかく流暢に、性格にことばを扱えるようになるために文型練習(パターン・プラクティス)をたくさんします。文型練習にはいろんな種類があるんですが、例えば代入練習を例にとると…
先生:ペン
学生:机の上にペンがあります。
先生:スマホ
学生:机の上にスマホがあります。
…
こんな感じの練習が代入練習という文型練習です。これを繰り返し行って無意識に言えるようになることを目指します。
選択肢1
正しいです。全体練習は必須。個別練習をすべきかどうかは授業時間にもよりますが、人数が少なければやったほうがいいです。みんなの発音を確認できるから。
選択肢2
オーディオリンガル・メソッドは音声・文法の正確さを特に重視しているので、細かい誤りでも指摘して直します。これは間違い。
選択肢3
オーディオ・リンガル・メソッドは口頭能力の育成が目的です。書く能力は重視していません!これは間違い。
選択肢4
あまりに人数が多いクラスだと全体練習がメインになってしまいます。時間を有効利用して個別の発話を際立させるために文型練習を学習者同士で行うこともあります。
したがって答えは1です。
問4 パターン・プラクティスの応答練習
パターン・プラクティスはたくさんあって、そのうち応答練習は教師のキューに対して指定された文型を用いて答える練習のことです。次の例がそう。これと同じものを探しましょう。
先生:釣りは好きですか?
学生:いいえ、好きではありません。
先生:登山は好きですか?
学生:はい、好きです。
1 受け答えをする応答練習
2 文型の一部に指示した言葉を入れる代入練習
3 同じ内容を繰り返させる反復練習
4 語を活用させる変形練習
答えは1です。
問5 シナリオ・プレイ
コミュニケーション能力、つまり対面の会話を伸ばせるような活動はどれでしょう。
選択肢1
ラポート・トークは自分の主観や感想を交えて相手の情緒に働きかけることで共感を得ようとする話し方のことです。
練習方法じゃないから間違い。
選択肢2
シナリオ・プレイは既に完成している脚本を演じることです。コミュニケーション能力の養成として効果的!
これが答え。
選択肢3
フォローアップ・インタビューはあるタスクが終わってからの学習者へ対するフォローアップ(支援や追跡調査)を目的としたインタビューのことです。
練習方法ではありません。
選択肢4
ディクテーションは再生したCDや教師が読み上げる音声を聞き取り文字化していく聞き取りの活動のことです。
聞いた音声を文字化していく練習なのでコミュニケーション能力の養成には向いていません。
答えは2です。




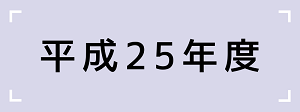
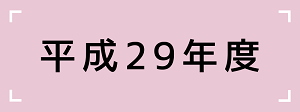
コメント