平成28年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題4解説
問1 ハ行転呼
現代のハ行は歴史的な音韻変化があって今のハ行になりました。
簡単にまとめると…
語頭のハ行は、奈良時代以前は[p](パピプペポ)でした。奈良時代ごろには[ɸ](ファフィフフェフォ)、江戸時代初期には[h]と[ɸ](ハフィフヘホ)に変わりました。現代と同じ[h]と[ç]と[ɸ](ハヒフヘホ)に変わったのも江戸時代だと言われてます。
語中・語尾のハ行は、奈良時代以前は[p](パピプペポ)でした。奈良時代ごろには[ɸ](ファフィフフェフォ)、平安時代中期には[β̞](ワウィウウェウォ)に変わりました。鎌倉時代には「ウィ」と「ウェ」が唇音を失い「イ」「エ」になります(ワイウエウォ)。江戸時代初期に「ウォ」が唇音を失い「オ」になり、現代の[ɰ]「ワイウエオ」になりました。
ちなみに[ɸ]から[β̞]になる過程をハ行転呼と呼んでいます。
つまり、現代の「上(うえ)」は「うぺ→うふぇ→ううぇ→うえ」と変化してきたみたい。
「川」は「かぱ→かふぁ(かは)→かわ」ということなのかな?
すいません、頑張ってまとめましたが間違いがありましたら教えてください。
問題に戻り…
ハ行音はかつて[p]両唇破裂音だったので答えは1です!
問2 ハ行転呼
ハ行音は平安時代中期、[ɸ]が語中・語尾に現れた場合は[β̞]で発音されるようになりました。
したがって答えは2です。
問3 ハ行音について
| ハ行 | 調音点 | 調音法 |
|---|---|---|
| は | 声門 | 摩擦音 |
| ひ | 硬口蓋 | 摩擦音 |
| ふ | 両唇 | 摩擦音 |
| へ | 声門 | 摩擦音 |
| ほ | 声門 | 摩擦音 |
| バ行/パ行 | 調音点 | 調音法 |
|---|---|---|
| ば/ぱ | 両唇 | 破裂音 |
| び/ぴ | 両唇 | 破裂音 |
| ぶ/ぷ | 両唇 | 破裂音 |
| べ/ぺ | 両唇 | 破裂音 |
| ぼ/ぽ | 両唇 | 破裂音 |
ハ行音は声門、硬口蓋、両唇などの摩擦音から構成されていますが、バ行音は全て両唇破裂音です。調音点も調音法も異なります。さらに、「は」は無声声門摩擦音、「ひ」は無声硬口蓋摩擦音、「ふ」は無声両唇摩擦音と、それぞれ調音点が異なります。
したがって答えは3です。
問4 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示)
選択肢1
この仮名遣いは、「ホオ・ホホ(頬)」「テキカク・テッカク(的確)」のような発音にゆれのある語について、その発音をどちらかに決めようとするものではない。
選択肢2
この仮名遣いは、科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。
選択肢3
この仮名遣いは、語を現代語の音韻に従つて書き表すことを原則とし、一方、表記の慣習を尊重して一定の特例を設けるものである。
この仮名遣いは、擬声・擬態的描写や嘆声、特殊な方言音、外来語・外来音などの書き表し方を対象とするものではない。
選択肢4
この仮名遣いは、主として現代文のうち口語体のものに適用する。原文の仮名遣いによる必要のあるもの、固有名詞などでこれによりがたいものは除く。
この仮名遣いは、擬声・擬態的描写や嘆声、特殊な方言音、外来語・外来音などの書き表し方を対象とするものではない。
したがって答えは4です。
問5 日本語の発音と表記
ハ行転呼とは、語中・語尾(語頭以外)のハ行音がワ行音に変化した現象のことです。選択肢1の助詞のヲを「お」ではなく「を」と表記するのは、ハ行転呼と関係のないことです。
したがって答えは1です。


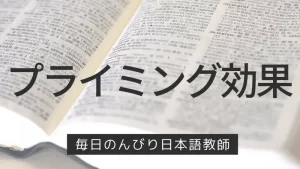

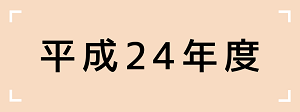


コメント
コメント一覧 (3件)
ハ行転呼について
語中 語尾のことはわかりましたが、語頭は、どうなったのでしょうか。
気になって、すみません。教えて下さい。
>大福もちさん
語頭については解説にすでに書いております。
ハ行転呼とは、[ɸ]がワ行音に変化することです。語頭の[ɸ]はワ行音に変化していません。
先程のハ行転呼は、川「かは」が「かわ」と字も読み方も変わったということですね。
すみませんでした。