平成27年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題8解説
問1 背景知識を活性化させる活動
「背景知識を活性化させる」という部分がプライミング効果を指しています。
プライミング効果とは、あらかじめ提示された事柄(プライム)により、それに関連する別の事柄(ターゲット)が覚えやすくなったり、思い出しやすくなることです。教室においては、あらかじめ教師が手本を見せたり、授業に関連する内容の雑談をしておくなどすることで学習者の学習効率を高めることができます。
この授業では現代の社会問題(格差社会)について話し合い、相手に伝え、自分の意見をまとめる活動をします。ですから本作業の前に現代の社会問題に関連する話題に触れておけば、そのあとの活動でプライミング効果が期待できます。
1 現代の社会問題とは関係ないです。
2 現代の社会問題とは関係ないです。
3 格差社会について知っていることや経験を話し合っておくと、そのあとプライミング効果が期待できます。
4 現代の社会問題とは関係ないです。
したがって答えは3です。
問2 論旨を正確に理解させるための指導
読解において、普段のスピードよりも速く読むことを速読と言います。速読は以下の2つに分けられます。
| スキャニング | 大量の文章から特定の情報を探し出すための読み方のこと。名簿から特定の名前を見つけたり、辞書で言葉の意味を調べるときなどに用いる読み方。スキャニングにはトップダウン処理がより必要とされる。 |
|---|---|
| スキミング | 文章の要点や全体の大意を理解するための読み方のこと。 |
1 正しいです。
2 正しいです。
3 要点を箇条書きにする活動なので、特定の情報を探し出すスキャニングよりもスキミングが求められます。
4 正しいです。スキミングをするだけでは正確に理解することはできませんが、スキミング後に再度詳しく読むよう指導しているので問題ありません。
したがって答えは3です。
問3 発表用スライドを作成する際に指導する内容
1 スライドでは分かりやすいように箇条書きや体言止めを用いるといいです。
2 スライドは文字だけではなく、視覚的に分かりやすいような作りが求められます。
3 見出しをつけて分かりやすいようにすべきです。
4 スライド内でわざわざ詳細に文字化する必要はなく、説明すべきことは口頭ですべきです。書きたいことをたくさん書いてるスライドは見にくい!
したがって答えは4です。
問4 発表で留意する点
1 正しいです。
2 発話の一部を強調して言うプロミネンスは、発表で用いるべきです。
3 フィラーを全く使用しないことは難しい…
4 原稿を一字一句読むのではなく、メモとして使うのが好ましいです。
したがって答えは1です。
問5 ディスカッションを活性化させるための働きかけ
ディスカッションは特定の答えのないテーマについて参加者で自分自身の意見を述べ合う活動です。
1 賛成と反対の立場があるテーマを用いるのはディベートです。
2 ディスカッションのテーマは答えが一つに絞ることができない、人によって答えが変わるようなものが採用されます。
3 ディスカッション中に流れを止めて文法指導するのは好ましくありません。コミュニカティブな活動では、活動後に細かく指導します。
4 正しいです。
したがって答えは4です。

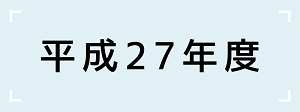



コメント