平成27年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題7解説
問1 結束性と一貫性
結束性や一貫性は談話分析における重要な概念です。この2つの線引きは明確ではありません。
| 結束性(cohesion) | 発話と発話の間に文法的・語彙的な結びつきがあること。指示詞でテクストの一部を指し示したり、先行詞を別の語で代用、あるいは省略したり、接続詞を使用したり、同義語や対義語、包摂関係などの語彙的な関係によって発話と発話の結束性が保持される。 |
|---|---|
| 一貫性(coherence) | 話者同士の共通認識や共有知識、常識などによって談話にもたらされる発話の繋がりや秩序のこと。 |
選択肢1
確かにフィラー(言いよどみ)はないですけど、終助詞が付加されることと一貫性が保持されることには関係ありません。
選択肢2
「は」と「が」の使い分けは文法的なことなので、結束性の保持と関係しています。
選択肢3
「そして」や「しかし」などの接続詞はありませんが、「たくさんの民族が住みます」では「瀋陽は」が、「清朝の皇帝が住みました」は「瀋陽の故宮は」が省略されていたりしてます。こういう語彙的な結びつきによって結束性が保持されています。
選択肢4
指示語は使用されていません。
したがって答えは3です。
問2 「住んでいます」になる理由
まず以下はこの問題を解くために必要な知識。
| 状態動詞 | 動作や変化ではなく、状態を表す動詞のこと。通常「~ている」の形をとらない。ある、いる… |
|---|---|
| 継続動詞(動作動詞) | 継続的なある動作を表す動詞のこと。「~ている」の形で動作が継続していることを表す。 読む、書く、食べる、降る、泣く、笑う… |
| 瞬間動詞(変化動詞) | 瞬間的に終わる動作を表す動詞のこと。「~ている」の形で結果の状態を表す。動作が行われる前後で変化が生じていることから変化動詞と呼ばれることもある。 死ぬ、つく、消える、見つかる、始まる、終わる、知る… |
| 第四種の動詞 | 形容詞的に用いられ、物事の性質や様子を表す動詞のこと。常に「~ている」の形で用いられる。そびえる、優れる、劣る、似る、澄む… |
で、「住む」はこの4つの何に分類されるかということがポイント。
「住む」についていろいろ検討してみると面倒です。例えば、「机の上にりんごがある」での「ある」は存在動詞なので状態動詞に分類されます。同じような文型をとる「ここに彼が住んでいる」も、「住んでいる」は存在動詞のように働いていてこれは状態動詞と言っていいと思います。一方で、「私はここに住み始めた」のようにアスペクト表現「~始める」をつけられる場合は継続動詞でしょう。典型的な瞬間動詞「結婚する」などは「結婚し始める」と言えないからです。
というわけで、「住む」はそれが使われている文でどのように働いているかによって状態動詞にも継続動詞にもなっていると思います。そして肝心のこの問題は「たくさんの民族が住んでいます」という文における「住む」の分類を聞いています。存在動詞は「【存在場所】に【存在主体】がある」などの文型をとりますが、この文にニ格はありません。この面から見るとこの「住む」は存在動詞、つまり状態動詞ではないと思われます。つまり継続動詞ではないか。「住む」が生活する、暮らすみたいな長時間に及ぶ動作を表していると考えられます。加えて、継続動詞に「ている」をつけるとその動作が進行中であることを表します。
したがって答えは1です。
ちなみに選択肢2には「居住した結果を表す」と書いてますけど、「~ている」で結果を表すのは瞬間動詞です。「住む」は瞬間動詞ではありませんので間違い。
問3 事前の原稿を準備することの利点
1 時間を与えて準備させることでスピーチの産出に集中できますが、時間がある分聞き手の存在にとらわれやすくなります。
2 スピーチの産出に集中できるので、学習した文型や語彙に意識が行きやすくなります。
3 時間が与えられるので、推敲する時間は十分確保できます。
4 準備時間が十分にあると、心理的負担は軽減されます。
したがって答えは1です。
問4 学習者に行う支援
1 似てる構成のスピーチのモデルを参考にすれば確かに原稿を作成しやすくなります。
2 正しいです。間違いなし。
3 自分の経験をもとに話を広げていくスピーチって魅力的ですよね。
4 時間は十分に与えられているので、周囲と相談して良い物を作り上げるほうがいいと思います。
したがって答えは4です。
問5 評価シートを使った自己評価
選択肢3
評価シートはその人にしか返却されませんので、他の学習者と比較することはできません。また、各項目5段階評価では、クラス内での位置を把握するには不十分です。
したがって答えは3です。

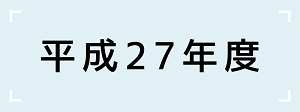
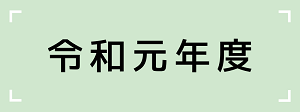



コメント