平成27年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題4解説
問1 「文」と「発話」の違い
話し言葉は「発話」、書き言葉は「文」という単位を用います。この理由として不適切なものを見つけます。
選択肢1
言いさし表現とは、「お願いがあるんですが。」など文の最後の部分を省略している表現のことです。言いさし表現は文としては不完全ですが、話し言葉で多く用いられ、一つのまとまりとなります。
選択肢2
話し言葉においてポーズを挟んだり、相手の言葉を繰り返したりするのはよくありますが、これを字にすると「文」として見なしにくくなります。
選択肢3
実際の発話として聞く「本当」はそのイントネーションによって意味が変わります。上昇調は疑問、平調では弁明などを表します。単語一つでそれ以上のことを表現でき、「文」のような単位になります。
選択肢4
文法的に正しいものは書き言葉でも話し言葉でも当然使われますが、仲間内で使うような砕けた表現、非文法的な表現も使われます。
したがって答えは4です。
問2 隣接ペア
隣接ペアとは、挨拶に対する挨拶、問いに対する返答、誘いや申し出に対する返答などのお互いにペアとなっている2つの発話のことです。また、隣接ペアの中に別の新たな隣接ペアが入ることを挿入連鎖と言います。以下の会話では、隣接ペア①と④の中に、隣接ペア②と③が挿入されています。
A:①暇? 遊びにいこう?
B:②バイトないの?
A:③うん、ないよ。
B:④じゃあいこっか。
問題文の隣接ペアはこんな感じになってます。
・「昨日の夜、何を食べましたか?」に対する「国の料理です。」
・「いつ?」に対する「昨日の夜。」
・「自分で作りましたか。」に対する「はい。」
「いいですねえ。」だけ浮いてます。間違えるとしたら「国の料理です」に対する「いいですねえ」ですが、「国の料理です」は「何を食べましたか」に対する応答です。隣接ペアの要素は他の隣接ペアの要素になりません。
したがって答えは2です。
問3 文と文の接続に関する誤用
「文と文の間を適切につなぎ、関連づける」のは重要だと言ってますので、文と文の間が適切につながれていないものを探します。
選択肢1
「知りません」だったら良いんですが、「知っていません」になっています。アスペクトに関する誤用です。
前件は知っていて、後件は知らない。その間に逆接の「でも」があるので文と文は適切に接続されています。
選択肢2
他の選択肢とは違い、この文だけ前件と後件の主語が異なっているので2つの事象をただ述べているだけのように感じられます。接続表現「しかし」などを間に入れれば「間に合わなかった」という意味をより強く全面に出せるんですけど。つまり接続表現がないことで文と文の結束性が弱まっているということです。
選択肢3
「少しも~ない」の文型を使ったほうがいいですが… その文型に関する知識がないのでしょう。
文と文はしっかり繋がっています。
選択肢4
「多くの外国人」というべきです。
前件と後件の間は自然に接続されてます。
選択肢2だけ接続表現がないので不自然になってます。
したがって答えは2です。
問4 談話全体の目的を考えて発話を組み立てる
談話の目的を考えて発話してるかどうかを見ます。
選択肢1
「傘持ってますか」で相手のことを気遣ってます。その気遣いに対して「ええ、ありがとう」と言ってます。これは良い感じ、問題ありません。
選択肢2
「忙しいですか」に対して「はい」か「いいえ」と答えるだけではなく、相手が何か用があると感じ取り、「何ですか」と聞き返しています。間接的に示された意図を感じ取っている返答です。
相手に何らかの意図を伝える際に、直接的な言い方を避け、間接的な言い方によって意図を伝えようとするのを間接発話行為と言います。例えば、小銭を借りるために「小銭貸して」というのではなく「小銭ある?」と言ったりするようなことです。あるないを聞いているんではなく、貸してほしいという意図を察して返答することが求められます。
選択肢3
この談話は何の問題もありません。
選択肢4
問いに対して答えるだけ…。 相手は自分に興味があっていろんな質問をしているのに何だか素っ気ないですね。質問されたら「リサさんはどうですか?」みたいな双方向のやり取りがあったほうが良いと思います。
したがって答えは4です。
問5 日本語の特質
文化を分類する際、高コンテクスト文化と低コンテクスト文化という考え方があります。
| 高コンテクスト文化 | 実際の言葉によりもその裏にある意味を察する文化のこと。重要な情報でも言葉に表わさず裏に隠して、相手に汲み取らせたり曖昧な言葉を使って表現する。世間一般の共通認識に基づいて判断したり、感情的に意思決定がなされる文化であり、いわゆる「空気を読む」ことが求められる。実際に発話された言葉は、会話の参与者の関係性、表情、状況、それまでの文脈などから判断して意味内容が変わり、特に日本はこの傾向がとても強い。 |
|---|---|
| 低コンテクスト文化 | 高コンテクスト文化とは逆に伝えたいことは全て言葉で説明する文化のこと。言葉以外や雰囲気で気持ちや情報を伝えることはせず、全て自らが発した言葉で表現する。この傾向が強いのはドイツ語圏とされており、またアメリカやカナダなどの歴史的に移民で成り立っている国にも多いとされてる。移民が多い国ではさまざまな考え方を持つ人々が集まっているため、文化ごとに異なる気持ちを汲み取るのではなく、分かりやすい言葉で伝えることが重視される。 |
1 正しいです。
2 高コンテクスト的特徴を持つ言語では、話された内容よりも話されていない内容に比重が置かれる傾向があります。
3 話し手が言語化しない部分を聞き手が察する傾向があるのは、高コンテクスト的特徴を持つ言語です。
4 予測がより多く働くのは高コンテクスト的特徴を持つ言語です。
したがって答えは1です。

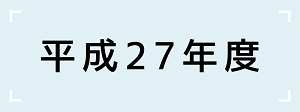

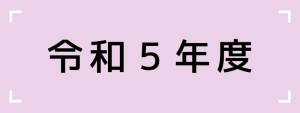
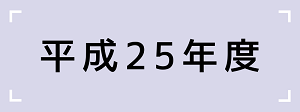
コメント
コメント一覧 (2件)
試験Ⅲ問題4
選択肢3と2について
2だけ接続表現がないことが回答の理由ですが、選択肢3も接続表現ありません。
[私は6時に駅に着きました。電車はすでに出ました(出ていました)] の方が、6時という時間の後に[すでに]という副詞が来ているので、時間の流れ的には繋がっているように思え、選択肢3より形態的には正しいような気がします。選択肢3は、接続表現は、どこと考えれば良いでしょうか。細かくてすみません!
>大福もちさん
ご指摘ありがとうございます。問題と解説についてもう一度確認いたしました。
文と文の繋がりということですので、おそらく談話の結束性について出題しているのだろうと思われます。
結束性は接続表現によって高まります。ですから「しかし」などの語がないことによって前件と後件のまとまりが薄くなっていると考えました。