平成25年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題11解説
問1 スクリプト
「服を見るためにお店に入った。しばらくしたら店員が寄ってきた。」
なぜ店員が寄ってきたんでしょう? 私たちの頭の中には、服屋のスクリプトがあります。「お店に入ったら、店員が寄ってきて、服を選んで、試着して、購入して、店を出る」というような、一連の出来事の典型的な順序に関する知識です。このスクリプトがあるので、おそらく100人中100人が「服をお勧めするため」「接客のため」と答えるはずです。
服屋に入ったことがない人、ジャングルの奥地にいるような人たちは服屋のスクリプトがないので、なぜ店員が寄ってきたのか理解できない可能性があります。経験がないと分からないんですよね。スクリプトは日常生活でも読解においても、状況の理解に大いに役に立っています。
1 修飾構造に関する知識は形式スキーマ
2 経験から蓄積された知識(背景知識)は内容スキーマ
3 物語文の文章構造についての知識は形式スキーマ
4 一連のできごとの流れについての知識なので、これがスクリプトです!
したがって答えは4です。
問2 橋渡し推論
文章中に明示されていない情報を予想することを推論といいます。推論は2つに分けられます。
| 橋渡し推論 | 直接表現されていないことを、文脈や既有知識によって理解すること。例えば、「向こうで一輪車を練習してた子供が大きい声で泣いていた。私は近づいて、『大丈夫?』と声をかけた。」では、「子供は一輪車から落ちて怪我をした」という推測がこれ。橋渡し推論は読解中に常に行われており、正しく推論できなければ理解に大きな支障が生じる。 |
|---|---|
| 精緻化推論 | 文章から読み取った事柄をもとに具体的なイメージを膨らませること。主人公の顔、髪型、表情、性格、様子を想像したりするのがこれにあたるが、実際想像したイメージは人によって異なる。橋渡し推論とは異なり、精緻化推論はできなくても理解には影響しない。 |
選択肢1
「それ」が指すものが「友達がくれたプレゼント」だと推測できなければ、前後の文の因果関係が理解できなくなります。正しく理解できなければ理解に支障をきたす推論は、橋渡し推論です。
選択肢2
今日徹夜するの明日のテストのために勉強するからです。「勉強するから徹夜する」と推測できなければ、前後の因果関係が分からず全体の理解もできません。橋渡し推論です。
選択肢3
新幹線に乗って京都で行ったんだと推測できなければ、なんで突然新幹線の話するの?ってなっちゃいます。正しく理解できなければ理解に支障をきたす推論は、橋渡し推論です。
選択肢4
富士山が見えるほど高いところに住んでるんだって想像するのは精緻化推論です。精緻化推論でのイメージは個人によって異なります。別に高層階に住んでいることを想像してもしなくても、文の理解には影響を及ぼしません。
ちなみに…「きれいだった」が富士山のことを指していると推論するのは橋渡し推論です。それができなければ何をきれいと言ってるんだろう?って理解ができなくなります。
したがって答えは4です。
問3 スキャニング
読解において、普段のスピードよりも速く読むことを速読と言います。速読は以下の2つに分けられます。
| スキャニング | 大量の文章から特定の情報を探し出すための読み方のこと。名簿から特定の名前を見つけたり、辞書で言葉の意味を調べるときなどに用いる読み方。スキャニングにはトップダウン処理がより必要とされる。 |
|---|---|
| スキミング | 文章の要点や全体の大意を理解するための読み方のこと。 |
1 トピックセンテンスとは、その段落で最も重要な主張をしている文のことです。全て読まなくてもそこだけ読み取れば段落の大意を把握できますので、このような読み方はスキミングです。
2 「大意をとる読み方」がまさにスキミングの説明です。
3 「必要な情報のみを拾い出す読み方」がまさにスキャニングの説明にあたります。
4 多読の説明です。
したがって答えは3です。
問4 補償ストラテジー
学習する際に用いる学習ストラテジーは以下の6つに分けられます。
| 直接 | 記憶 | 記憶するために用いる暗記、暗唱、復習、動作などの記憶術。新しい知識を蓄え、蓄えた知識の想起を支えるもの。 |
|---|---|---|
| 認知 | 記憶した情報の操作や変換に用いるストラテジー。リハーサルしたり、既知の要素を組み合わせて長い連鎖を作ったり、分析・推論するなど。または、より理解を深めたりアウトプットするためにメモ、要約、線引き、色分けなどをして知識を構造化するなど。 | |
| 補償 | 外国語を理解したり発話したりする時に、足りない知識を補うために用いるストラテジー。知識が十分でなくても推測やジェスチャーなどによって限界を越え、話したり書いたりできるようになる。 | |
| 間接 | メタ認知 | 学習者が自らの学習を管理するために用いるストラテジー。自分の認知を自分でコントロールし、自ら学習の司令塔となって学習過程を調整したり、自分自身をモニターする。 |
| 情意 | 学習者が学習者自身の感情、態度、動機などの情意的側面をコントロールし、否定的な感情を克服するためのストラテジー。自分を勇気づけたり、音楽を聴いてリラックスしたりするなど。 | |
| 社会的 | 学習に他者が関わることによって学習を促進させるストラテジー。質問したり、明確化を求めたり、協力したりするなど。 |
単語や音、文法などの言語知識を用いて、細かい部分から徐々に理解を進めていく言語処理方法をボトムアップ処理といいます。言語能力が不十分な学習初期の学習者がトップダウン処理を用いて理解しようとするのは、言語学習ストラテジーの補償ストラテジーです。補償ストラテジーとは、足りない知識を補うために用いるストラテジーです。分からない言葉を文脈から推測したりするのがこれに当たります。
したがって答えは4です。

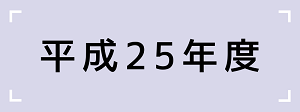

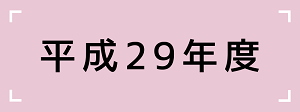

コメント