平成25年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題12解説
問1 非母語話者はよく行い、母語話者は通常行わない行為
選択肢1
相手に分かりやすいように話すのは母語話者が普通行うことです。フォリナートークとか、ティーチャートークとか。
選択肢2
相手が分からない可能性のある単語や文法を回避するのが事前調整です。これは母語話者が行うことです。
選択肢3
ジェスチャーは母語話者も非母語話者もします。
選択肢4
母語話者は文法的な誤りを犯さないので、自分が間違っているかどうかモニターしてません。
これは非母語話者がすることです。
したがって答えは4です。
問2 フォリナートーク
フォリナートークとは、母語話者が非母語話者に対してする話し方のことで、簡単な語彙や文法を扱って分かりやすいように話すのが特徴です。スピードも遅くなったり、繰り返したりします。
選択肢1
フォリナートークは母語話者の話し方のことです。母語話者の外見がどうであるかはフォリナートークを誘発する要因になりません。
選択肢2
非母語話者の外見が外国人っぽいなと母語話者が判断した場合、その母語話者はフォリナートークを使うかもしれません。
相手の外見が外国人っぽければ、もしかしたら日本語上手じゃないかな?って思い、フォリナートークを誘発する可能性があります。
選択肢3
非母語話者があまり話を理解できなければ、もっと簡単な言葉にしたりゆっくり話さないと伝わらないと思い、フォリナートークを誘発する可能性があります。
選択肢4
非母語話者の言っていることがあまり理解できなければ、非母語話者のレベルもあまり高くないと想像できるので、フォリナートークを誘発する可能性があります。
したがって答えは1です。
問3 言語管理
文章の冒頭のネウストプニーといえば言語管理理論の提唱者。
したがって答えは3です。
この問題は単純に知識を問う問題です。それを知らないと答えを選ぶことは難しそう。
問4 規範
ここで「規範」という言葉が出てきてるのでまず説明します。
接触場面のインターアクションでは、その場面ごとに基底規範が設定されています。多くの場合はその場面で使用される言語の母語話者の規範が適用されます。
例えば、二人の日本語母語話者がこんなやり取りをしてます。
A:昨日の半沢直樹、つまらなくなかった?
B:そう? 俺的にはめっちゃつまるけど。
A:つまるってなんだよ(笑)
ここでは「つまらない」の「ない」を派生接辞(否定形)とみなして元々存在したであろう原型に戻す操作をし、「つまる」という言葉を生み出してます。「つまらない」の否定形は本来「つまらなくない」なんですが、これは一種の言葉遊びのようなもので「つまる」になってます。Aもそれがちゃんと「おもしろい」という意味なんだと理解できます。だから「つまるってなんだよ」って突っ込んでます。
しかし、これがもし日本語教師と学習者の間の雑談だったらどうでしょうか。
日本語教師:昨日の半沢直樹、つまらなくなかった?
学習者:そうですか? 私的にはめっちゃつまるんですけど。
日本語教師:「つまらなくない」ですよ。
この非母語話者は「つまらない」の反対は「つまる」、本当にそう思っている可能性があります。だから教師はそれが間違いであることを指摘しました。
つまり…
母語話者同士で話すときはお互い完璧な日本語を使っていると無意識で分かっているので、もしおかしな表現が使われたとしても言葉遊びの一種だと思い、わざわざ訂正するようなことはしません。日本語のレベルが同じなので、模範的な日本語(規範)に従わずとも意思疎通できるからです。
でも非母語話者がいる場合は両者の日本語のレベルが違うので、レベルの低いほうは従うべきルール(規範)ができます。2つ目の会話では、教師の規範が会話の規範になっています。母語話者のほうが日本語が上手ですから、下手なほうは上手なほうに従わなければいけなくなるわけです。そして上手なほうは下手なほうの変な表現、誤用に敏感になり、指摘しやすくなります。これは母語話者同士の会話ではほぼ見られません。
このように、規範というのはその場にいる母語話者と非母語話者の関係で生まれてきます。
そしてその規範は言語規範、社会言語規範、社会文化規範の3つに分けられます。
| 言語規範 | 接触場面において設定される基底規範のうち、話者が従うべき音声や語彙、文法などの規範のこと。 |
|---|---|
| 社会言語規範社会言語学的規範 | 接触場面において設定される基底規範のうち、ある場面で用いるべき適切な表現に関する規範のこと。目上には「食べましたか?」ではなく「召し上がりましたか?」を用いるべきなど。 |
| 社会文化規範 | 接触場面において設定される基底規範のうち、その社会、文化に根付いている一般常識的な行動様式の規範のこと。「目上には上座を譲る」や「初対面ではハグをする」など。 |
選択肢1
教師と学生なら言葉を教える教えられるの関係ですから言語規範が適用されやすく、上司と部下なら礼儀関係の社会言語規範が適用されやすくなります。その場面の参加者の力の差異によって選択される規範は変わります。
選択肢2
正しいです。コミュニケーションが成立している場合、多少の誤りは見過ごされたりします。
選択肢3
最初はあまり気にせず見過ごしていたミスが頻発するようになったので指摘するというケースもあります。
選択肢4
母語話者は通常規範を犯しませんので、規範は意識されにくくなります。非母語話者と接触する場面の方が意識されやすいです。
上述した「つまるんですけど」がこれを説明する良い例です!
したがって答えは4です。
問5 社会言語規範と社会文化規範
「相手の話し方が友達に話すような調子でなれなれしい」というのは、上の表だと社会言語規範から逸脱したものです。
「お礼を言うタイミングに違和感を感じたりする」のは、社会文化規範からの逸脱です。
したがって答えは3です。

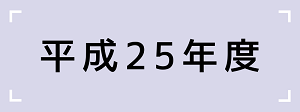

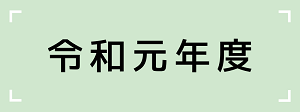
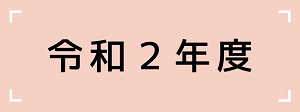
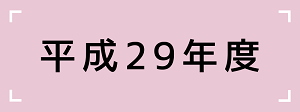

コメント