平成24年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題11解説
問1 協調の原理
問題文には量の公理、質の公理…と4つ書かれてます。これはグライスが提唱した会話を円滑に進めるための原理「協調の原理」です!
| 量の公理 | 必要な情報だけ与えるようにせよ。余分な情報は与えるな。 | 「授業は何時ですか?」に対して「もうすぐです」は情報が少なく、「4時0分0秒です。」は余計な情報が付加されているため、量の公理に反する。 |
|---|---|---|
| 質の公理 | 嘘や根拠の乏しいことを言わず、真実を言え。 | 嘘や皮肉、メタファーなど。「手伝ってくれてありがとう。逆に仕事が増えたよ」みたいな嘘とか。 |
| 関係の公理(関連性の公理) | 関係あることを言え。 | 「あとどのくらいで終わらせられる?」に対する「人手が足りなくて…」は関係の公理に反する。 |
| 様態の公理(様式の公理) | 不明瞭で曖昧な言い方は避け、簡潔に順序立てて言え。 | 「好きなような、嫌いなような…」は様態の公理に反する。 |
これは単純に知識を問う問題でした。
したがって答えは3です。
問2 公理
行くかどうかの質問に対して、行くとも行かないとも言わずにレポートについて触れています。一見すると関連性の公理に反しています。
したがって答えは3です。
問3 誘いへの返答に見られる特徴
選択肢1
「一緒に行かない?」に受諾するなら「いいよ」って言えばいいんですが、「うーん… いいよ」みたいに言いよどみが入るケースは少ないです。
選択肢2
「一緒に行かない?」に受諾するとき、まず「いいよ」と返答することが多いです。「今日バイトないし、暇だし、いいよ」みたいな前置きを入れるケースは少ないです。
前置きが多くなるのは断るときです。「ちょっとバイトあって、いけない。ごめんね」みたいに。
選択肢3
その通りです。「ちょっとバイトあって、いけない。ごめんね」みたいなことです。
選択肢4
断るときは理由などを述べるために長い表現になりやすいです。
したがって答えは4です。
問4 関係なことも実は関係ある
「映画、見に行かない?」に対してミナは「明日レポートの締め切りだから」というのは一見すると関係性の公理に反しています。じゃあ何でこんなこと言ったんでしょう。
ミナはこのように言えばマリに意図が伝わると思っているので、レポートの締め切りの話をしています。文章中でもあるように、マリはその文脈から考慮して「行けない」ことを察するに至っています。
つまり、関係性の公理に反しているのにコミュニケーションが成り立つのは、実は関係ないことを言っているわけじゃないからです。関係あることを言っているはずだという前提に基づいて文脈から推測し、相手の意図をくみ取ります。
したがって答えは2です。
問5 含意
問4でもある通り、「エ」に入れるべき言葉は含意です。相手の含意(意図)をくみ取ってコミュニケーションは行われています。
したがって答えは1です。
問6 公理
どちらに行くのか聞いているのに、具体的な場所を述べずに「ちょっとそこまで」と言うのは不明瞭で曖昧な表現なので、様態の公理(様式の公理)に反しています。また、必要な情報を提供していないので量の公理にも反しています。
この問題は量の公理にも様態の公理にも反していると考えられるので、答えは4だとするのは間違いだと思います。だって、『入門 語用論研究―理論と応用』(研究社)には、「ちょっとそこまで」は量の公理に反しているって書かれてるんですもん。
この問題は美しくありません!!!

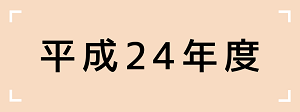


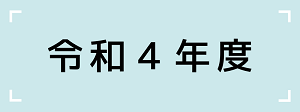

コメント