平成27年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題8解説
問1 カテゴリー化
カテゴリー化とは、目にした対象のパターンを最も類似した過去の記憶に基づいて、その対象の持っている属性や性質を推測することで生じる分類のことです。人は認知能力に限りがあるため、カテゴリー化により最小の認知的努力で最大の情報を得ようとします。集団はカテゴリー化されることが多く、それによって内集団と外集団の違いが鮮明となることで偏見や差別が生まれるとされます。
1 カテゴリー化は外見によらず、異なる集団の間で発生します。「あいつらは~だ!」みたいなやつです。
2 その国の文化的側面からカテゴリー化がされることもあります。例えば、黒人と白人に見られるカテゴリー化はアメリカでは結構すごいですが、日本ではそうでもありません。
3 対象を自分の中で分かりやすく分類するのがカテゴリー化です。複雑にするための作用ではありません。
4 人は誰でもカテゴリー化を自然に行っています。正しいです。
したがって答えは4です。
問2 ステレオタイプ
ステレオタイプとは、多くの人に浸透している、特定の集団に対する先入観や思い込み、固定観念のことです。「眼鏡をかけてる人は勉強できる」や血液型占いなどがこれにあたります。ここに否定的な評価や感情が加わることで「◯◯人は✕✕だ」のような偏見や差別が生じます。
1 「Xさん」は個人です。ステレオタイプは集団に対して生じます。
2 「中国人」に対するステレオタイプ
3 「女性」に対するステレオタイプ
4 「ドイツ人」に対するステレオタイプ
ステレオタイプは特定の集団に対して起こるもの。選択肢1は個人に対するものなのでステレオタイプではありません。
したがって答えは1です。
問3 内集団と外集団
問題文によると、自分が所属する内集団と、それ以外の外集団の境界線をはっきりさせるのがカテゴリー化だそうです。
選択肢1
内集団バイアスについての記述です。文章中にも後述されています。
人は自分が属する集団に対して贔屓する傾向があるんですね。
選択肢2
内集団バイアスにはこんな例もあります。自分が属する内集団に対する批判があった場合、自分が批判されていなくても対抗する態度を見せることがあります。これは非当事者攻撃と呼ばれてます。ネットの炎上、延焼などもこれが原因とか。逆に内集団が高く評価されると、自分が直接評価されているわけではないのに評価されている感じがする。これも内集団バイアスです。この選択肢は正しいです。
選択肢3
この間現職の議員が職場に来て、講演会があるのでポスターを貼ってほしいとお願いされました。その人、人柄ちょっと感じ悪いなあという印象を受けたんですが、この印象はやがてその議員の派閥や党全体に対する印象に変わることがあります。その議員と所属する党などは私からすると外集団。この集団はみんなそうだと思うことがここでいう「外集団を均質的に捉える」ことです。はじめは個人に対する印象だったのに、不思議ですね。
この選択肢は外集団と内集団の関係が逆です。
選択肢4
カテゴリー化では外集団の成員を均質的に捉える一方、内集団の成員の性質ははっきり捉えられます。よって内集団の成員の方が、それぞれ異なって認識されます。
したがって答えは3です。
問4 外集団に対する偏見や差別
特定の集団に対する先入観や思い込み、固定観念(ステレオタイプ)に否定的な評価や感情が加わると偏見になります。その偏見が原因となって伴った行動が差別です。
選択肢1
正しいです。外集団を貶めて自分を高めるみたいなことです。
選択肢2
カテゴリー化は無意識で行われます。
選択肢3
そもそもステレオタイプは自分の知らないものを過去の経験に基づいて大体理解しようとする働きであり、知らないものに対して起こりやすいものです。
例えば報道やネットの情報などから影響を受け、「A国の人たちはみんな〇〇だ」のようなステレオタイプないし偏見ができあがったとします。しかし実際A国の人とコミュニケーションする機会があったり友達になったりすると、「A国の人でもそうではない人もいる」ということに気づきます。知らないものは均質的に捉え、知っているものは詳細に捉えます。
ステレオタイプは外集団に対して起こるものです。
選択肢4
利害関係がなくても、その外集団を蔑む感情があれば偏見や差別につながります。
したがって答えは1です。
問5 カルチャー・アシミレーター
1 コンフリクト・マネジメント
組織においてマイナスに捉えられがちな利害の衝突・対立を組織の活性化や成長の機会と捉え、解決することです。
2 オピニオン・ギャップ
参加者の間にある意見の差のことです。
3 クリティカル・シンキング(批判的思考)
目の前にある情報を鵜呑みにせず、本当に正しいのかと疑うことで考えを深め、最適解に辿り着こうとする思考方法のことです。
4 カルチャー・アシミレーター
文化の違いを感じさせるエピソードに対する複数の解釈を通じ、人々の解釈の違いを学んでいく形式の異文化トレーニングの一つです。異文化で起きた問題の事例を読み、自ら原因を考え、自分の考えに合うものを選択肢から選びます。正しいものを選べなかった場合はその文化を考え直すきっかけになり、こうして異文化理解を深めさせます。
したがって答えは4です。

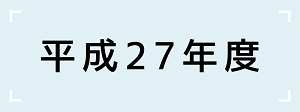


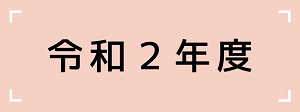

コメント