平成25年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題3解説
問1 日本語のテンス
テンス(時制)とは、時間を表す文法形式のことです。日本語ではル形が現在と未来を表し、タ形が過去を表します。
| 過去 | 現在 | 未来 |
|---|---|---|
| 食べた | 食べる | 食べる |
選択肢1
ここで述べられている動的述語とは、主語の動作や行為を表す述語のこと。状態動詞以外の動詞が述語に来る動詞述語文のこと。また、静的述語とは、主語の状態や性質を表す状態動詞や形容詞、「~Nです」などの形を取るの述語のこと。言い換えると、名詞述語文、形状詞述語文、形容詞述語文、状態動詞が述語に来る動詞述語文のこと。
彼は英語を話す。(動的述語)
机にりんごがある。(静的述語)
彼はかっこいい。(静的述語)
彼は学生だ。(静的述語)
テンスについて考えるとき、動的述語のタ形「食べた」は過去で、静的述語のタ形「あった/いた」も過去を表します。テンスに”完了”という概念はありません。”完了”という概念は、ある動作や出来事がどの局面にあるかを表す文法形式のアスペクト(相)で示されます。この問題は「日本語のテンス」についての問題ですので、誤りです。
選択肢2
動作動詞「食べる」はル形で未来を表します。状態動詞の「ある」はル形で現在を表します。
選択肢3
主節のテンスは発話時との時間的前後関係のみで決まるため、絶対テンスと呼ばれます。
従属節のテンスは発話時との時間的前後関係を表さず、主節時との時間的前後関係で決まるため、相対テンスと呼ばれます。
彼は「試験に合格した」と言っていた。
主節の「彼は言っていた」は、発話時よりも過去の出来事なのでタ形を用いています。一方、従属節の「試験に合格した」は、主節の「言う」という動作が行われたときよりも前に起きた出来事なので、タ形を用いています。
彼は「絶対合格してやる」と言っていた。
主節は例文(1)と同様に、発話時よりも過去の出来事なのでタ形を用いています。一方、従属節の「合格する」は、主節の「言う」という動作が行われたときよりも未来に起こる出来事なので、ル形を用いています。
選択肢4
選択肢3で述べたように、主節のテンスは発話時を基準とする絶対テンス、従属節のテンスは主節時を基準とする相対テンスです。
したがって答えは2です。
問2 一般的な文法にのっとって説明しにくい「から」
格助詞「から」の用法は6つあります。
| 範囲の起点 | 会社から家まで1時間かかる。 |
|---|---|
| 材料 | 醤油は大豆から作る。 |
| 動作の出どころ | 彼から本を貸してもらった。 |
| 受身文の動作主 | 私は先生から叱られました。 |
| 物事の原因 | 一瞬の迷いから失点した。 |
| 根拠 | 状況から見ても明らかだ。 |
1 いずれにも分類されません。
2 範囲の起点
3 範囲の起点
4 範囲の起点
選択肢1だけが、一般的な格助詞「から」の用法にない使い方ですので、単純に説明がしにくくなっています。
したがって答えは1です。
問3 接客時に頻繁に用いられる表現
「ほう」は場所や方向を表すときに用いるものですが、接客時には「500円のほうからお預かりします」「お箸のほう、お付けしますか」などと使われることがあります。この「ほう」は文法的な説明が難しいです。
また、「になります」は「秋になる」のように変化を表す文法ですが、接客時には「こちらがご注文の◯◯になります」のように使われることがあります。この「になります」も文法的な説明が難しいです。
こういうのはいわゆる「マニュアル敬語」っていうやつです。
したがって答えは2です。
問4 日本語の敬語体系
敬語は以下の5つに分類されます。
| 素材敬語 | 尊敬語 | 相手側又は第三者の行為・ものごと・状態などについて、その物を立てて述べるもの。 例)いらっしゃる、おっしゃる、なさる、召し上がる、お使いになる、御利用になる、読まれる、始められる、お導き、御出席、(立てるべき人物からの)御説明、お名前、御住所、(立てるべき人物からの)お手紙、お忙しい、ご立派 |
|---|---|---|
| 謙譲語Ⅰ | 自分側から相手側又は第三者に向かう行為・ものごとなどについて、その向かう先の人物を立てて述べるもの。 例)伺う、申し上げる、お目に掛かる、差し上げる、お届けする、御案内する、(立てるべき人物への)お手紙、御説明 | |
| 対者敬語 | 謙譲語Ⅱ(丁重語) | 自分側の行為・ものごとなどを、話や文章の相手に対して丁重に述べるもの。 例)参る、申す、いたす、おる、拙著、小社 |
| 丁寧語 | 話や文章の相手に対して丁寧に述べるもの。 例)です、ます | |
| 敬語に準じるもの | 美化語 | ものごとを、美化して述べるもの。 例)お酒、お料理 |
上の表の素材敬語とは、話題の中の人物(素材)への敬意を表すものです。
対者敬語はその場にいる人物(素材)に対するものではなく、自分側の行為・ものごとなどを、話や文章の相手に対して丁重に述べるものです。
選択肢1
文中に登場する人物に用いる敬語は素材敬語、聞き手に対して用いる敬語は対者敬語です。
選択肢2
「行く」「来る」「いる」の尊敬語は「いらっしゃる」で共通しているので、それだけでは確かに意味の判別が難しくなります。
選択肢3
現代日本語の敬語は状況や場面によって尊敬語になったり謙譲語になったりする相対敬語です。
韓国語は状況や場面によらず、話題の人物が自分より目上の場合は敬語を使う絶対敬語です。
選択肢4
美化語は物事を美化して述べるだけで、誰かへの敬意を示すものではありません。
したがって答えは3です。
問5 「お値段、サービスさせていただきます」を誤用とする立場の根拠
「~させていただく」は「トイレを使わせていただけませんか?」のように、話し手の利益になることに対して用います。ここでは話し手に「トイレを使う」という利益がもたらされるため、この表現は間違いではありません。
「お値段、サービスさせていただきます」では、話し手がお客さんにサービスをして、恩恵を受けるのはお客さんです。「~させていただく」が表す利益の対象が話し手ではなくなっているため、規範的な立場からは誤用とみなされます。
したがって答えは1です。

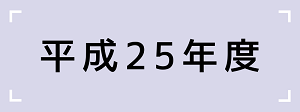

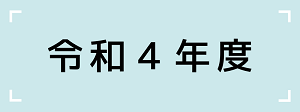


コメント