平成24年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題12解説
問1 規範的な立場から見て不適当な敬語
1 一般的に目上に「ご苦労様」は失礼です。「お疲れ様でした」を使うべきです。
2 目上の能力を問う「話せますか」のような言い方は失礼ですが、ここでは「お話になりますか」ですから問題ありません。
3 問題ありません。
4 問題ありません。
したがって答えは1です。
問2 隣接ペア
1 スモール・トーク(small talk)
会話における本題に入る前に話す、天気について触れたり、相手の近況を伺ったりといった他愛もない会話のことです。挨拶的な役割を果たし、コミュニケーションを円滑にする役割があります。
2 最小対(minimal pair)
亀/kame/と駄目/dame/のように、ある1つの音素の違いによって意味の変わる語のペアのことで、ミニマルペアとも呼ばれます。その音の違いに集中させて発音を練習する練習をミニマルペア練習と言います。これはオーディオリンガル・メソッドで用いられる練習の一つです!
3 隣接ペア(adjacency pair)
挨拶に対する挨拶、問いに対する返答、誘いや申し出に対する返答などのお互いにペアとなっている2つの発話のことです。「おはよう」に対する「おはよう」、この2つの発話が隣接ペアになります。
4 ターン・テイキング(turn taking)
二人以上が参加する会話において、話し手が発話を始めてからその話者が交替するまでの発話のひとまとまりをターンと呼びます。会話では誰かが話し終わったら別の人が話し、また別の人が話し… という話者の交替が順番に起きます。この現象のことをターンテイキング(turn-taking)、あるいは話者交替と呼びます。
「おはよう」に対する「おはよう」は、隣接ペアですね。
したがって答えは3です。
問3 丁寧さの指標
1 目礼よりもおじぎの方が丁寧です。
2 丁寧な言葉がモーラ数(拍数)が長めです。「大変申し訳ありませんが、手伝っていただけませんか?」と「すいませんが、手伝ってください」では、モーラ数が長い前者のほうが丁寧が印象を受けます。モーラ数が長いかどうかは丁寧さの指標となります。
3 挨拶を省略するのは丁寧とは言えません。
4 午後は「こんにちは」を使うべきです。
したがって答えは2です。
問4 交感的な機能
「天気が良いですね」「こんにちは」などの挨拶は何か情報のやり取りをしているわけではなく、実際の伝達機能を持たない表現です。これらは話し手と聞き手の関係を深めるために用いる交感的言語表現と呼ばれます。
「挨拶=交感的表現」とそのまま覚えておくといいです。これを知ってるかどうかの問題。
したがって答えは4です。
問5 挨拶の指導をする際の留意点
選択肢1
極端な例ですが、カスタマーサービスなどでは「お電話ありがとうございます。~~~、カスタマーサービスの〇〇と申します。」みたいな長い挨拶も見られます。初級では「こんにちは」などの初歩的な挨拶だけ触れればいいんですが、上級になってこういう場面に遭遇するような学習者には、長めの挨拶の指導をしたほうがいいでしょう。
選択肢2
挨拶を繰り返し練習させることは良いですが、日本人に合わせる必要まではありません。その人が持つ文化を尊重すべきです。
選択肢3
正しいです。日本語母語話者では一般にこのような挨拶の形式が取られますよと教えてあげることは必要です。そのうえで学習者に日本の規範に従うのか、母国のやり方を維持するのか、中間的なやり方をするのかを判断させるほうがいいです。日本人の行動様式、習慣、価値観を強要するのは良くありません。
選択肢4
挨拶といっても「こんにちは」というだけではなく、実際はお辞儀をしたり、握手したりなんていう非言語的な動作も伴います。併せて指導するのが好ましいです。
したがって答えは3です。

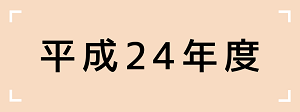


コメント