平成29年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題5解説
問1 プロジェクトワークにおけるタスクの意味
プロジェクトワークはコミュニカティブな活動の一つです。学習者が主体となって計画をし、資料や情報を集めたりして、グループごとに一つの作品にまとめたりします。例えば報告書、新聞、発表、映像などを作るなどなど..。
ここでいうコミュニカティブな活動とは、学習者間のコミュニケーションを重視した活動のことです。学習者間にはインフォメーションギャップやオピニオンギャップがあり、それぞれタスクの中でどのように振る舞うかを自分で決めることができます。相手の反応(フィードバック)が含まれた、複数の技能を用いる実際のコミュニケーション場面に近い活動をします。活動中教師は細かい指導を行わず、活動が終わった後にまとめて行います。
1 未習の言語形式に触れることは良いことですが、だからといって文法学習を増やしてしまうとコミュニカティブではなくなってしまいます。
2 プロジェクトの目的はいったん決めたら変更することはありません。変えたらみんな困っちゃいます。
3 特定の技能に特化したタスクを与えるのではなく、四技能をまんべんなく使って達成するタスクを与えたほうがいいです。
4 正しいです。コミュニカティブな活動は現実のコミュニケーション場面に近い活動をします。
したがって答えは4です。
問2 学習者同士話合わせる目的
プロジェクトワークでは、学習者が主体となって行います。
したがって答えは2です。
問3 インタビュー時の聞き手の行動
1 相手の言ったことを「~ということですね」と言い換えて、理解していることを伝えるとインタビューは円滑に進みます。
2 分からないときは「分かりません」ではなく、具体的に聞くべきです。
3 相手の話し中に相槌を打つことは、聞いていることを示すためにも必要です。
4 「うん」などと言ってうなずくほうがいいです。
したがって答えは1です。
問4 教室外活動を行う効果
選択肢2の規範的な日本語という部分が誤りです。
規範的な日本語とは、正しい文法、正しい表現を重視した日本語のことです。これは普通教室で教えられるものですが、教室外では非文法的な表現もよくよく使われます。
したがって答えは2です。
問5 マップを配布する目的
1 このプロジェクトワークの目標は「マップをオープンキャンパスで配布する」ことですので、実際に配布することが目標です。
2 実際に配布することで実際の日本人と触れ合えますので、コミュニケーションの場となりえます。
3 プロジェクトワークでは現実性の高い作品を作りますので、作成したマップが来訪者の役に立てるかどうかを検証するのも目的の一つです。
4 訂正作業は配布前、および配布後のフィードバックで行います。来訪者にしてもらうことじゃないです。
したがって答えは4です。

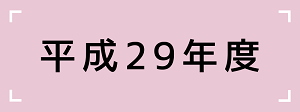


コメント
コメント一覧 (2件)
問3の4の選択肢ですが、うんと言ってうなずくほうが良いなら、4も正解になるのでは?
>かんさん
聞き手に「聞くときは一切無言で、絶対頷かないようにしてください」と指導するのは間違いです。「うん」「はい」などと相槌を取りながら頷いたりしたほうがいいでしょう。
「無言で」と「うなづかないようにする」を切り離して考えてください。