平成26年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題15解説
問1 訪日外客数
2013年 訪日外客数(総数)はこうなってます。
| 順位 | 国名 | 累計(人) |
|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 2,456,165 |
| 2 | 中国 | 1,314,437 |
| 3 | 台湾 | 2,210,821 |
したがって答えは1です。
参考:日本政府観光局(JNTO) 国籍/月別 訪日外客数(2003年~)
問2 過去時制を表す動詞の語形変化
語形変化っていう言葉があるので、言語の形態的類型を思い出します。
| 膠着語 | 実質的な意味を担う語幹に接辞を接続することによって語形変化する言語のこと。「食べる」の語幹「tabe」に屈折接辞「ru」がつくような変化を持つ。 | トルコ語、ウイグル語、ウズベク語、モンゴル語、日本語、朝鮮語(韓国語)、フィンランド語、インドネシア語、エスペラント語… |
|---|---|---|
| 屈折語 | 文法的機能を表す形態素が、語の内部に分割できない形で埋め込まれる言語のこと。つまり、語そのものが変化する言語のこと。 | ラテン語、ギリシア語、ロシア語… |
| 孤立語 | 全ての語が語形変化しない言語のこと。 | 中国語、ベトナム語、ラオス語、タイ語、クメール語… |
| 抱合語 | 特に動詞に他の意味的または文法的な要素が接続され、語だけで文に相当する意味を表現することができる言語のこと。 | アイヌ語… |
韓国・朝鮮語は日本語と同じ膠着語なので、語形変化があります。中国語は孤立語なので語形変化しません。この点から見ると答えは4に絞れます。
インドネシア語については知らなくても解けるような問題に作りにしてくれていたみたいです! やさしいですね。
ちなみにインドネシア語はwikiによると膠着語らしいです。でもこんな記述が。
インドネシア語に動詞の時制による語形変化はない。
膠着語なのに時制による語形変化はない? へーというしか…
まあこの点から見ても答えは変わらず4ですね。
問3 日本語指導が必要な外国人児童生徒への言語支援
答えは3です。
2014月1日に学校教育法施行規則の一部を改正する省令等が施行されました。
参考:学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)
この改正によって、「海外から帰国した児童生徒や外国人児童生徒,その他主たる家庭内言語が外国語であるなど日本語以外を使用する生活歴がある児童生徒のうち,学校生活を送るとともに教科等の学習活動に取り組むために必要な日本語の能力が十分でないもの」を対象に特別の教育課程を実施できるようになりました。特別の教育課程では、日本語の能力に応じた特別の指導(日本語指導)が行われます。
問4 ポルトガル語・スペイン語を母語とする児童生徒数の増加
1990年6月の出入国管理及び難民認定法の改正施行に伴い、「定住者」の在留資格が創設されたことで日系三世までの就労が可能となり、ポルトガル語・スペイン語を母語とする日系人の来日が増えました。
したがって答えは1です。
問5 日本語教育の推進
詳しくは日本語教育の推進に当たっての主な論点に関する意見の整理について(報告)を参考にしてください。
選択肢1
76ページにはこのような記述があります。
カリキュラム案等の活用について,研修を実施したり,モデルを作成したりするほか,カリキュラム案等について指導する人材の確保や生活者事業を通して広く活用してもらうことや,コーディネーターによる日本語教育実施団体へのフォローなど多面的に検討を行っていく必要があるのではないか。その際,カリキュラム案等の活用状況や改善に関する希望について継続的に実態把握を行うことが必要である。
また,カリキュラム案等の活用のターゲット(対象や活用の仕方等)を明確にする必要があるのではないか。その上で,その内容や示し方等の改善について検討することが必要ではないか。
選択肢2
102ページにはこのような記述があります。
地域により日本語教室の開設状況や人材確保の状況は大きく異なる。人材について,ボランティアの果たす役割は大きいが,高齢化等の理由により,確保が困難なところが出てきており,教える側に若い人や外国人などが参加し,継続的に日本語教育を行えるように検討することが求められる。また,ボランティアとして日本語指導やコーディネートに関わる人の知識や経験,属性等は多様であるが,実態の把握,整理を行った上で,その役割や待遇,配置などについて検討が必要ではないか。
選択肢3
59ページにはこのような記述があります。
外国人の定住化が進んだことを受け,来日当初の生活に必要な日本語に加え,読み書きや子供の教育に関わるための日本語や就労のための日本語など,よりレベルの高いものが求められるようになっている。しかし,地域における日本語教育では来日当初の生活に必要な日本語や初級段階の日本語学習機会の提供にとどまっていることが多いのではないか。
選択肢4
82ページにはこのような記述があります。
地域における日本語教育において,外国人がどのようなニーズを持っているかということを踏まえた上で,日本語教育に関する人材に求められる内容について整理することが必要である。
また,実態として日本語教育に関する人材の基準は多様であり,地域によって日本語教室やそこで日本語を教える者,コーディネーターの捉え方は大きく異なるが,地域における日本語教育に関する新たな資格を設定することは適切か,さらに,ボランティア(日本語教育能力検定試験の合格者や大学で日本語教育について学んだ者等も含む)が大きな役割を担っている現状に照らして一定の線引きを行うことは,問題がないか検討が必要である。
その上で,新たな資格を作るのがよいか,それとも既にあるものをより充実したり,活用したりするのがよいか検討が必要である。仮に新たな資格を作るとなった場合は,実施者についての検討が必要である。
コーディネーターについて触れてはいますが、コーディネーターの資格を設定する話はありません。
答えは4です。
正直こんな問題出されても絶対答え分かんないですよ。雑な出題とは言いませんけど、一介の日本語教師がこんな報告書読み込んでるわけないでしょ…





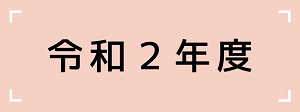
コメント