平成25年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題5解説
問1 コースデザインの流れ
コースデザインはニーズ・レディネスの調査、シラバスデザイン、カリキュラムデザインの3段階です。
| ニーズ調査 | 目標言語調査 | その学習者が将来遭遇するであろうと予測される場面において、母語話者は実際どのような日本語を使用しているのかを調査すること。 |
|---|---|---|
| 目標言語使用調査 | その学習者が実際にどのような日本語を使用しているかを知るための調査。 | |
| レディネス調査 | 学習者の学習条件を調査・分析すること。調査・分析対象は、自分の意思や都合では決められない学習者の母語や母文化、年齢、今までの学習期間、経済的要因、学習環境などの外的条件と、学習者の個人的な条件である学習スタイル、日々の学習時間、現在のレベル、外国語学習経験などの内的条件に分けられる。 | |
| シラバスデザイン | ニーズ分析、レディネス分析の結果に基づき、そのコースで学習者に何をどう教えるのか、授業計画(シラバス)を検討する段階。 | |
| カリキュラムデザイン | コース実施に必要な事柄の確定をする段階のこと。教授法、教室活動、教材の選定・作成、授業の流れ、学習項目の順序や時間配分などの具体的な教案、テストや評価について決めます。 | |
カリキュラムデザインは、教授法・教室活動を決めた後に教材を選定します。教室活動、例えばロールプレイやろうと計画した後でないとロールプレイに関する教材を作れませんから、順序はこうなるのは当たり前。そういうものだと覚えてください。
したがって答えは4です。
問2 各課の構成
1 課を構成するために必要な情報です。
2 課を構成するために必要な情報です。
3 課を構成するために必要な情報です。
4 クラス規模や学習者の母語は、ニーズ分析の段階で把握していることです。
したがって答えは4です。
問3 コースに合わせた手直し
リライトとは、教科書の分かりにくい表現を別の表現に書き換えることです。年少者日本語教育では子どもに分かりやすい日本語にリライトしたりします。
1 教科書の元々のねらいや主題に沿った書き換えは問題ありません。それらに沿わない内容に書き換えるのは望ましくありません。
2 既習の語彙や文法しかない教材は言語習得を促進しません。年少者と言えど、文脈で推測できるレベルの未習語彙や文法を含めるべきです。
3 各課の内容を踏襲した書き換えは必須。内容は無視すべきではありません。
4 年少者日本語教育のリライトでは、子どもに分かりやすいような日本語にリライトすべきです。正しい!
したがって答えは2です。
問4 リソースへのセルフ・アクセスのための環境作り
ここでいうリソースとは、言語学習の中で何か問題が発生したときに、その問題を解決するための資源のことです。参考書や教師などがこれにあたります。これらのリソースに学習者自身にアクセスさせる環境作りで留意すべき選択肢を選びます。
1 正しいです。カタログを作っておけば、学習者が困ったときそれを調べられます(セルフ・アクセスを促せます)。
2 リソースはその種類や分野によって分類して配置したほうがアクセスしやすくなります。
3 学習で発生した問題を解決するため、書庫は近くにあるとより役に立ちます。セルフ・アクセスしやすくなります。
4 ある語彙の意味が分からなくて辞書を引いたのに、その説明も日本語で書かれていて解決できなかったら意味ないです。母語で日本語を学ぶ環境も用意してあげたほうがいいです。
したがって答えは1です。

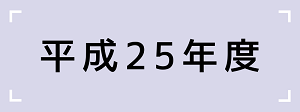



コメント