平成24年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題5解説
問1 認知的で創造的な過程
選択肢1
その通り。聞こえてくる音と意味を関連付けないと理解できません。しかも聞こえてくる音だけ理解するんじゃなくて、明示されていない部分まで推測しないといけません。これが高度に認知的で創造的な過程ってやつです。
選択肢2
聞こえてくる音を正確に捉えないと理解もできませんけど、表記のバリエーションは視覚的なものなので聴解で気にする必要ありません。理解には直接関係ないし。
選択肢3
情報が必要かどうかを識別する必要はありますが、聴解問題中に自ら語を作ったりする必要はありません。
選択肢4
文脈から情報を補うのは必要ですが、言語行動と非言語行動を区別する必要はありません。
したがって答えは1です。
問2 前作業
授業の流れは以下の3段階。
| 前作業 | 本作業を行う前の準備段階のこと。本作業で行うタスクに関連する話題を提示することで、学習者の背景知識を活性化させ、学習効率を高めたりする段階。 |
|---|---|
| 本作業 | その授業の中心となるタスクを行う段階のこと。 |
| 後作業 | その授業のまとめの段階のこと。 |
前作業を行う理由は、背景知識を活性化させるためです。これはプライミング効果に関係があります。
プライミング効果
あらかじめ提示された事柄(プライム)により、それに関連する別の事柄(ターゲット)が覚えやすくなったり、思い出しやすくなることです。教室においては、あらかじめ教師が手本を見せたり、授業に関連する内容の雑談をしておくなどすることで学習者の学習効率を高めることができます。
選択肢1の「背景知識を活性化するため」がポイントです。
したがって答えは1です。
問3 本作業
どれも本作業でやることにように見えますが、この問題は聴解問題の活動の流れについて問う問題です。
選択肢2だけは聴解に加えて筆記要素もあるので妥当性(そのテストが測定しようとしている事柄を的確に測定しているかどうかの度合い)が低くなってます。聴解だけに集中できるようなタスクを行うべきです。
したがって答えは2です。
問4 後作業の再話
再話とは、読解や聴解後に自分が理解したことを自分の言葉で話すことです。話すことが目的なのではなく、話すことによって記憶に定着させることが目的です。この点注意が必要です!
選択肢4、再話の目的はまさにこれ。再話の目的知ってますか?っていう問題は何度か出題されてます。間違えないようにしましょう。
したがって答えは4です。
問5 初級レベルの聴解問題の作り方
1 正しいです。聴解問題の内容に依存した問題にすべきです。
2 正しいです。テストの妥当性を保つためにも、聞く以外の能力が必要のないような問題を作ったほうがいいです。
3 未習語を含めることで内容を推測させられます。そうして少しレベル上げたほうがいいです。
4 正しいです。最初に問いを聞いているので、何を聞き取ればいいのか明確になります。
したがって答えは3です。

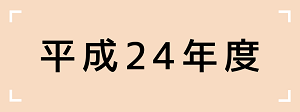

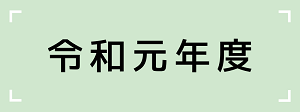
コメント